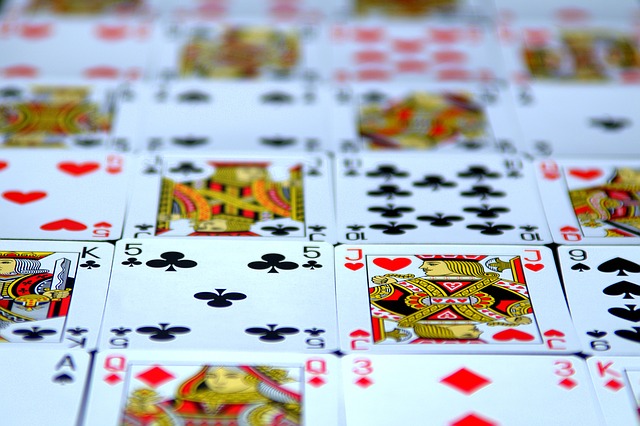 ジョブカードとは、個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職などを促進するために設けられたカードで、生涯を通じたキャリア・プランニング及び職業能力証明で活用されます。
ジョブカードを利用すれば、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進、訓練の必要性が明確になるなどのメリットがあります。
研修系の助成金の要件として、ジョブカードの作成が義務付けられている場合があります。主にキャリア・コンサルタントのコンサルティングでジョブ・カードが利用されます。
研修系の助成金と言えば、厚生労働省の人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)が特に有名ですが、この助成金も原則としてジョブ・カードの写しの提出が必要になります。
今回は、人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)にジョブ・カードを提出する際の注意点について詳しく説明します!
※研修系助成金に関する記事はこちら
助成金を受給できる研修はどんな研修ですか?
外部の研修を受講すると支給されるおすすめの助成金!
研修の為に休暇を取ると助成金?
「うちの研修を受ければ、助成金が入るから実質無料!」は本当?
ジョブカードとは、個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職などを促進するために設けられたカードで、生涯を通じたキャリア・プランニング及び職業能力証明で活用されます。
ジョブカードを利用すれば、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進、訓練の必要性が明確になるなどのメリットがあります。
研修系の助成金の要件として、ジョブカードの作成が義務付けられている場合があります。主にキャリア・コンサルタントのコンサルティングでジョブ・カードが利用されます。
研修系の助成金と言えば、厚生労働省の人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)が特に有名ですが、この助成金も原則としてジョブ・カードの写しの提出が必要になります。
今回は、人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)にジョブ・カードを提出する際の注意点について詳しく説明します!
※研修系助成金に関する記事はこちら
助成金を受給できる研修はどんな研修ですか?
外部の研修を受講すると支給されるおすすめの助成金!
研修の為に休暇を取ると助成金?
「うちの研修を受ければ、助成金が入るから実質無料!」は本当?
1.旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)
 旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。
しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。
平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
旧キャリア形成促進助成金(制度導入コース)は、平成28年度をもって廃止され、平成29年4月1日より「人材開発支援助成金(制度導入コース)」になった助成金です。
しかし、採択された当時はまだキャリア形成促進助成金(制度導入コース)だったという理由などで、支給申請自体は今でも有効な事業所が存在しています。
平成31年4月1日以降、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の内、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
2.人材開発支援助成金(制度導入コース)
人材開発支援助成金(制度導入コース)は、平成29年度にスタートした新しい助成金です。 人材開発支援助成金(制度導入コース)の内、セルフ・キャリアドック制度の助成金は、平成30年3月31日までに計画を提出した事業所までをもって、廃止されています。 ですが、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)同様に、支給申請自体は今でも有効の事業所がまだ存在します。 こちらもキャリア形成促進助成金(制度導入コース)と同じく、平成31年4月1日以降、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をする場合に、ジョブ・カードの写しの提出が必要となります。3.ジョブ・カードの個人情報は隠していい?
 ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。
個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。
厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。
ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。
確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。
ジョブ・カード一式を提出する際は、どうしても個人情報が気になりますよね。
個人情報を隠した場合は、黒塗りをして目隠しすることが可能です。
厚生労働省によれば、「セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請におけるジョブ・カード一式(写)については、キャリア・コンサルティングを受けた労働者の個人情報の記載事項について、労働者が非開示を希望する記載事項を黒塗りにしたものでも差し支えない」とのことです。
ただし、「各シートの労働者氏名及びセルフ・キャリアドックの実施日時、キャリア・コンサルティング実施者の所属、氏名等を除く」とも言及していますので、この部分に関しての黒塗りはNGです。
確かに、支給要件に直接影響する部分ですので、当然と言えば当然です。
4.まとめ
このジョブ・カードの提出ですが、原則は平成31年4月1日以降となっています。 しかし、東京、沖縄などの労働局では、先行して要提出としているようです。 人材開発支援助成金(制度導入コース)やキャリア形成促進助成金(制度導入コース)を申請する際は、提出先の労働局に確認することをお勧めします。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


 助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!
助成金なうでは、皆様のお役に立つ助成金・補助金をどんどん追加していきます!ご愛顧の程、お願いします!

 労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。
①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
②1年以下の懲役または50万円以下の罰金
③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
④30万円以下の罰金
有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。
社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。
労働基準法に違反した場合、以下の罰則を受けます。
①1年以上10年未満の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
②1年以下の懲役または50万円以下の罰金
③6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
④30万円以下の罰金
有罪判決になった場合、前科持ちとして大きな十字架を背負わされることになり、社会的信用を大きく損ないます。
社会的信用を失えば、会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかける恐れもあります。



 補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
補助金は中小企業庁ばかりが出しているわけではありません。国土交通省でも補助金の公募があります。
国土交通省では、スマートウエルネスを推進するために、住民の健康や幸福感向上に気よする住環境の整備を行った方に対して、支援を行っています。
具体的には、高齢者、障害者、子育て世帯などが安心安全に暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修、介護予防、健康増進、多世代交流など対して、補助金を支給しています。
平成31年度の概算要求は275億円となり、主に3つの事業に分かれています。
■サービス付き高齢者向け住宅整備事業
■セーフティネット住宅改修事業(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)
■人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業(新設)
以下、各事業について、詳細を説明します。
 サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
サービス付き高齢者向け住宅の普及を目的としたもので、サービス付き高齢者向け住宅の整備や改修にかかる費用を補助します。
①住宅の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1戸につき180万円
②新築住宅の場合
補助率:10分の1
上限額:1戸につき90万円~135万円
②高齢者生活支援施設の改修の場合
補助率:3分の1
上限額:1施設につき1000万円
④新築の地域交流施設などの場合
補助率:10分の1
上限額:1施設につき1000万円
 平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備
平成30年度に新設されました。
高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認められた事業の実施について、その費用の一部を支援します。
①建設工事費(建設・取得)の場合
補助率:10分の1
②改修工事費の場合
補助率:3分の2
③技術の検証費
補助率:3分の2
④具体例
○多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点(共同リビング、こども食堂、障害者就労の組合せ等)の整備
○介護予防や健康維持に資する高齢者向け住宅(IOT活用による効果的な見守り、地域との連携・交流の工夫など)
○早めの住み替えやリフォームに関する相談拠点(高齢期に適した住まいや住まい方のアセスメントなど)の整備

 求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
 ②募集期間
随時
②募集期間
随時
 県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで


 「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
 労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更
労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更


 ものづくり補助金は、公募を開始する前に、まず事務局を募集して決定します。
事務局は以下6点の条件を満たす必要があります。
①日本国において登記された法人であること
②本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
④本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること
⑤予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
⑥予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
※⑤~⑥については、「暴力団に所属または関与していない」、「破産手続きをしたことがない」、「不正したことがない」という条件だと考えれば問題ないです。
ものづくり補助金は、公募を開始する前に、まず事務局を募集して決定します。
事務局は以下6点の条件を満たす必要があります。
①日本国において登記された法人であること
②本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
④本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること
⑤予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること
⑥予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること
※⑤~⑥については、「暴力団に所属または関与していない」、「破産手続きをしたことがない」、「不正したことがない」という条件だと考えれば問題ないです。
 平成30年度のものづくり補助金事務局の募集は、2018年12月28日~2019年1月23日に行われました。
応募者は中小企業庁のものづくり補助金担当部署に、以下の書類を持参または郵送します。
①公募申請書
②事業実施計画書
③申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書
⑤運営に必要な事務費の内訳
平成30年度のものづくり補助金事務局の募集は、2018年12月28日~2019年1月23日に行われました。
応募者は中小企業庁のものづくり補助金担当部署に、以下の書類を持参または郵送します。
①公募申請書
②事業実施計画書
③申請方法、周知方法、申請書類等の事業実施方法に関する説明書
④実施体制及び事業に関する事業部等の組織に関する説明書
⑤運営に必要な事務費の内訳
 事務局の選定は、有識者からなる外部評価委員会が、以下の項目を総合的に評価して審査します。
①事務局としての適格性
○法人格の有無
○本事業の類似事業の受託実績
○組織の本事業に関する専門知識・ノウハウなど
②事業実施計画
○スケジュールの妥当性、効率性
③事業実施方法
○補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性
④事業実施体制と事務費用
○要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施
○適切な経営基盤、一般的な経理処理能力
○事務費の金額の妥当性
事務局の選定は、有識者からなる外部評価委員会が、以下の項目を総合的に評価して審査します。
①事務局としての適格性
○法人格の有無
○本事業の類似事業の受託実績
○組織の本事業に関する専門知識・ノウハウなど
②事業実施計画
○スケジュールの妥当性、効率性
③事業実施方法
○補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性
④事業実施体制と事務費用
○要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割分担の実施
○適切な経営基盤、一般的な経理処理能力
○事務費の金額の妥当性

 失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
 ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
 ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。
ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。































