 助成金を受給するには就業規則を作成していることが大前提です。
しかし中には、就業規則を作成すること自体に対して支給する助成金もあります。
東京都足立区の就業規則作成助成金です。
以下主な要件となります。
助成金を受給するには就業規則を作成していることが大前提です。
しかし中には、就業規則を作成すること自体に対して支給する助成金もあります。
東京都足立区の就業規則作成助成金です。
以下主な要件となります。
1.助成対象者
次のすべてに該当することが必要です。 ①足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要。) ②過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り) ③同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと2.助成対象経費
就業規則の作成に要した社会保険労務士等への作成委託費用
3.助成金額
助成率:1/2 上限額:5万円4.申請期間
該当就業規則が足立労働基準監督署に届出を受理されてから1年以内 申請は先着順で受付け、予算額に達し次第締め切られます。 なお、助成金としては珍しく、社会保険労務士による代行申請は不可となります。そのため後方支援として社会保険労務士に携わってもらい、実際の書類提出は自社という形になります。5.必要な申請書類
①所定の申請書 ②該当の就業規則が管轄の労働基準監督署に届出を受理されたことを証する書面 ③上記就業規則についての従業員の意見書または、従業員に対し説明会などで周知したことを証する書類(意見書の場合は、原本とその写し) ④助成対象経費の支払いが証明できる書類 ⑤助成対象経費の明細が証明できる領収書(原本とその写し)6.まとめ
就業規則を作成する場合は社会保険労務士に依頼するのが通常ですが、当然その報酬を支払う必要があります。 その報酬の一部が助成金として返ってくるので、まだ創業したてで資金が不足している事業者にとっては大変助かることと思います。 就業規則の作成を検討している事業者の方は、お住いの自治体でも同じような助成金が出ていないか確認してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


 A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。
A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。

 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
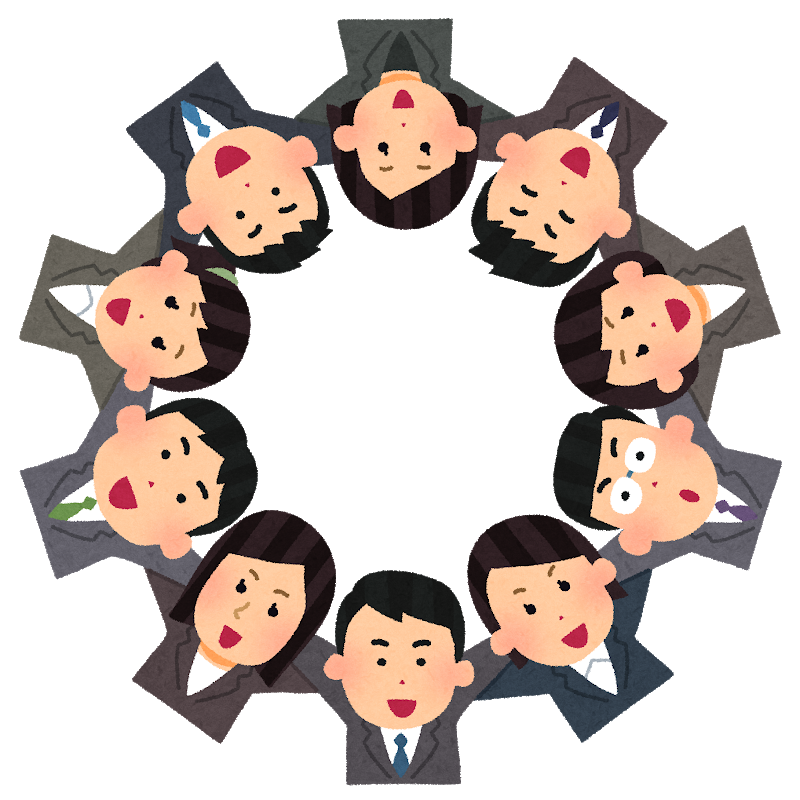 いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。






























