 昨年2018年は、その年の漢字が「災」となったとおり、集中豪雨などの災害が多発しました。
そのため、官庁や昨年被災した地域の自治体では、さまざまな復興支援に取り組んでいます。また、被災していない自治体でも、もし災害が発生しても被害が拡大しないよう、防災対策に積極的に取り組んでいます。
たとえば、東京都では防災関係の大型助成金としてBCP実践促進助成金を設けています。
この助成金は、中小企業などが策定したBCPを実践するための設備等の導入にかかった費用の一部を助成しています。
以下主な要件となります。
※BCP(Business continuity planning)とは?
直訳すると「事業継続計画」です。災害やテロ攻撃などの緊急事態が発生しても事業を継続または早期復旧できるよう、非常時の行動や手続きをまとめておく計画のことを指します。
昨年2018年は、その年の漢字が「災」となったとおり、集中豪雨などの災害が多発しました。
そのため、官庁や昨年被災した地域の自治体では、さまざまな復興支援に取り組んでいます。また、被災していない自治体でも、もし災害が発生しても被害が拡大しないよう、防災対策に積極的に取り組んでいます。
たとえば、東京都では防災関係の大型助成金としてBCP実践促進助成金を設けています。
この助成金は、中小企業などが策定したBCPを実践するための設備等の導入にかかった費用の一部を助成しています。
以下主な要件となります。
※BCP(Business continuity planning)とは?
直訳すると「事業継続計画」です。災害やテロ攻撃などの緊急事態が発生しても事業を継続または早期復旧できるよう、非常時の行動や手続きをまとめておく計画のことを指します。
1.助成対象事業者
都内において事業を営んでいる中小企業者及び中小企業団体で、策定されたBCPを実践する者2.助成対象事業例
・自家発電装置、蓄電池等の設置 ・災害発生時に従業員等の安否確認を行うためのシステムの導入 ・データ管理用サーバー、データバックアップシステムの導入 ・飛散防止フィルム、転倒防止装置等の設置 ・従業員用の備蓄品(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、浄水器等の購入 ・水害対策用物品設備(土嚢、止水板等)の購入・設置 ・耐震診断 など ※都内に本社があり、都外の事業所に設置する場合は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。 ※通常の業務でも使用できる設備等の導入は対象外です。
3.助成対象経費
・設備等の購入・設置工事等の費用 ・建物の耐震診断に要する費用4.助成額
助成率:2分の1(小規模企業は3分の2) 上限額:1500万円(下限10万円)5.申請期間
2019年5月7日(火)~11月25日(月)6.まとめ
今回の東京都のもの以外にも、官庁や各自治体では防災関係の助成金・補助金を多数公募しています。 「もしもの時に備えて防災対策をしたい!」とお考えの方は是非助成金なうで防災と検索してみてください! ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!















 (1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(1)本人収入が月8万円以下
(2)世帯全体の収入が月25万円以下
(3)世帯全体の金融資産が300万円以下
(4)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5)全ての訓練実施日に出席している
(6)世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
(7)過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない








 (1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること
(1)~(4)のいずれの条件も満たす必要があります。
(1)東京圏からの移住者
(2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人に応募し、計画期間中に雇い入れられた方
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること


 (1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助上限額:1施設につき400万円
補助率:
10分の9(客席面積100平方メートル以下の場合)
5分の4(客席面積が100平方メートルより大きい場合)
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
補助上限額:1施設につき150万円
補助率:5分の4
(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
補助上限額:1施設につき400万円
補助率:
10分の9(客席面積100平方メートル以下の場合)
5分の4(客席面積が100平方メートルより大きい場合)
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
補助上限額:1施設につき150万円
補助率:5分の4

 2次締切までの期間は2か月半ほどあり、前年度と比べて長期間です。
加えて、予算も前年度と比べて200億円ほど少ないです。
それらを踏まえて考えると、2次公募はあまり期待できません。
採択されたけれども辞退した案件が多く出るなどのことがない限り、まず2次募集はないと考えてよいでしょう。
仮に2次募集があったとしても余った予算が少額であれば2次募集の採択率は非常に厳しくなることは間違いないと思います。
したがって、ものづくり補助金の申請を考えているのでしたら、何としても今回の公募に申請してください。
2次締切までの期間は2か月半ほどあり、前年度と比べて長期間です。
加えて、予算も前年度と比べて200億円ほど少ないです。
それらを踏まえて考えると、2次公募はあまり期待できません。
採択されたけれども辞退した案件が多く出るなどのことがない限り、まず2次募集はないと考えてよいでしょう。
仮に2次募集があったとしても余った予算が少額であれば2次募集の採択率は非常に厳しくなることは間違いないと思います。
したがって、ものづくり補助金の申請を考えているのでしたら、何としても今回の公募に申請してください。



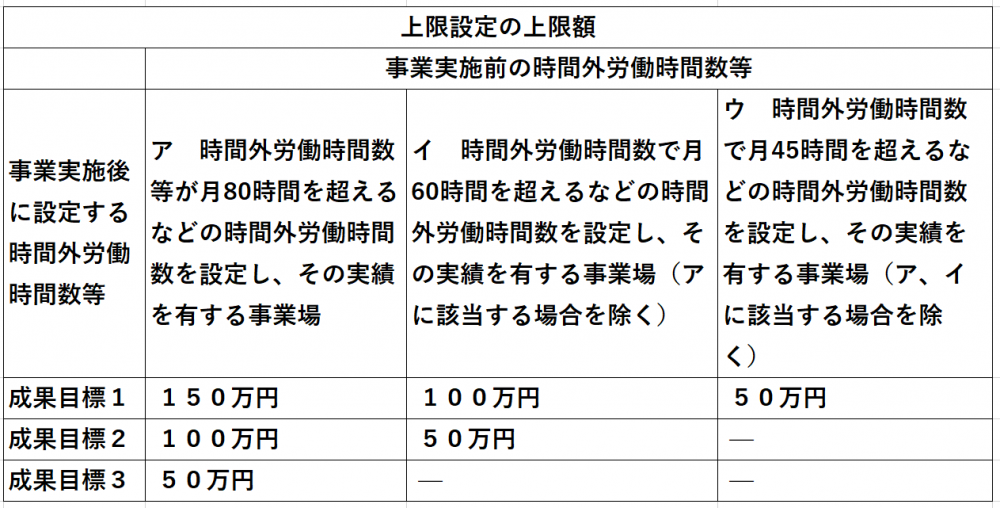
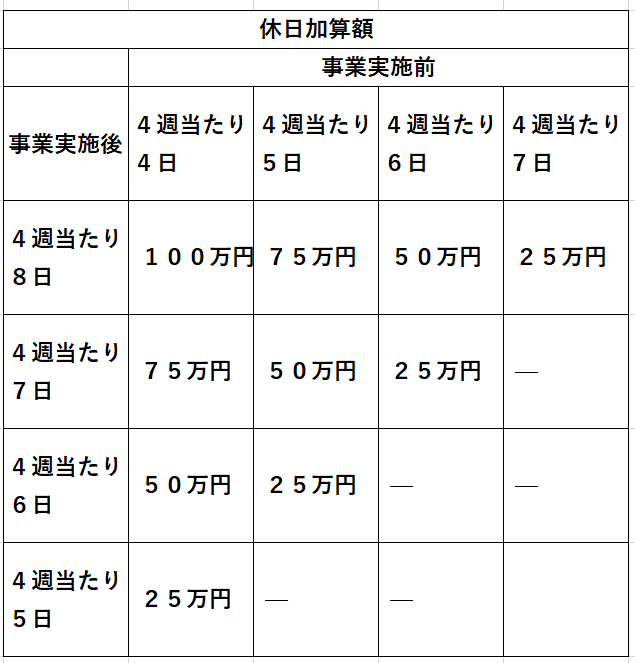 (3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
(3)対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
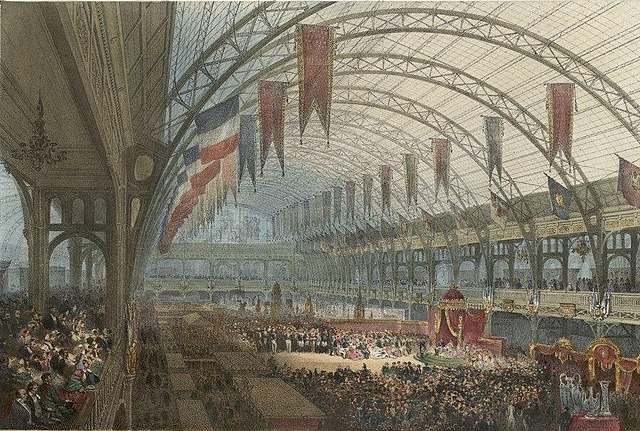




 (1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。
(1).先導的ユーザーへの導入費用助成
助成率:2分の1
助成上限額:200万円
(2).展示会出展・広告費の助成
助成率:2分の1
助成上限額:150万円
(1)で実用化した技術・製品等に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。
(1).先導的ユーザーへの導入費用助成
助成率:2分の1
助成上限額:200万円
(2).展示会出展・広告費の助成
助成率:2分の1
助成上限額:150万円

 (1)補助率
4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
(2)補助上限額
1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。
(1)補助率
4分の3
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品は1/2を補助対象経費とし、これに補助率3/4を乗じます。
※物品費は補助率1/2となります。
(2)補助上限額
1事業者あたり150万円
※機器の総額の上限は20万円となります。
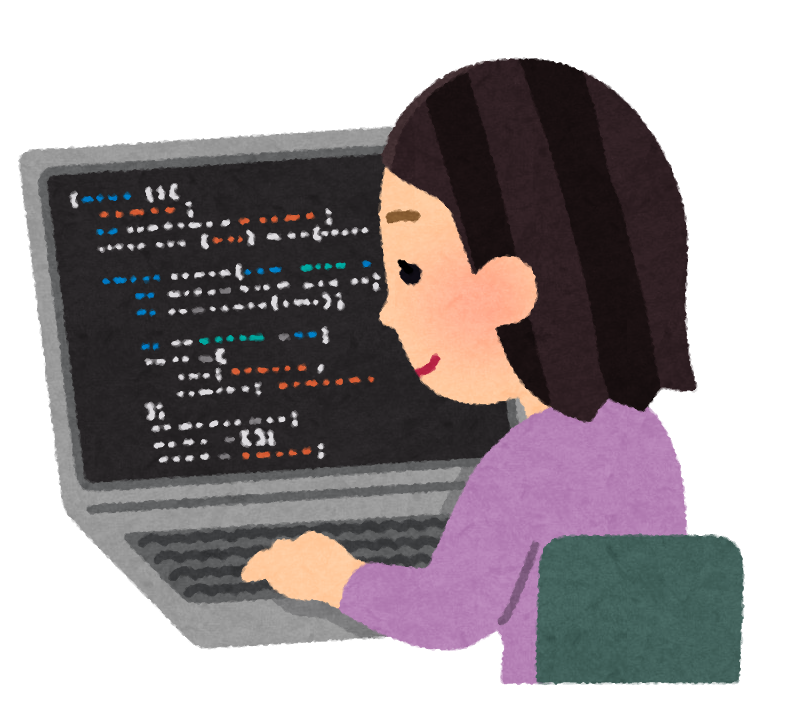



 ※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。
※1 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。
※2 廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額。





 (※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア,申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a,職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b,職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c,委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ,支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。








 2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。
ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。
しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。
50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。
2017年の厚生労働省の発表によると、ストレスチェックの実施報告書の提出がない事業所の割合は2割近くありました。
ストレスチェック制度未実施の事業場が直接罰則を受けることはありません。
しかし、労基署への報告を怠ると、労働安全衛生法違反と見做され、罰則が課せられます。
50人以上の事業場において、ストレスチェックの実施報告を行わなかった場合、または実施したと虚偽報告を行った場合、最大50万円の罰金支払いを命じられます。
 50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。
しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。
以下主な要件となります。
50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、実施しなくても罰則を受けることはありません。
しかし、厚生労働省では、小規模の事業場が積極的にストレスチェックに取り組めるよう、助成金を支給しています。
以下主な要件となります。


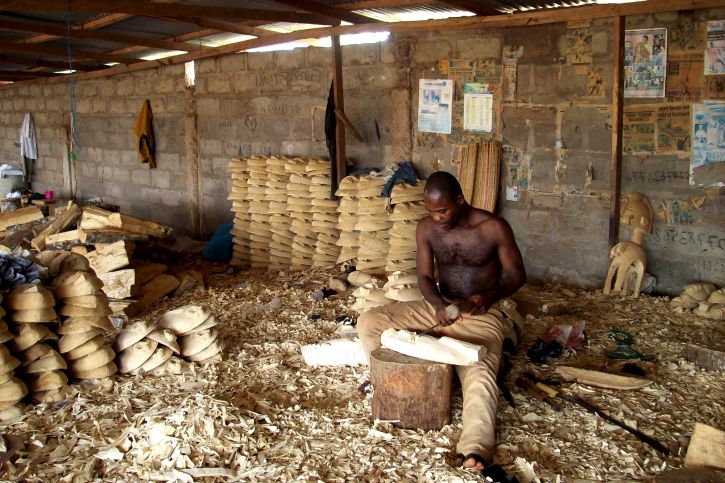
 申請書の書き方で大きく変わったのは、ページ数の制限がついたことです。
これまでは特にページ数の規定がなく、自由に書くことができました。
しかし、今回は、応募申請書は、様式1、2合わせてA4用紙計15ページ(別紙含む)までとなりました。
決まった形式部分を除けば、実質8ページ中にすべて表現しなければなりません。
したがって、必要なことを網羅しつつ、図や写真も用いながら、コンパクトに短いページにまとめることが必要になりました。
さらに、文字の大きさも10.5ポイントで記載することになりました。
申請書の書き方で大きく変わったのは、ページ数の制限がついたことです。
これまでは特にページ数の規定がなく、自由に書くことができました。
しかし、今回は、応募申請書は、様式1、2合わせてA4用紙計15ページ(別紙含む)までとなりました。
決まった形式部分を除けば、実質8ページ中にすべて表現しなければなりません。
したがって、必要なことを網羅しつつ、図や写真も用いながら、コンパクトに短いページにまとめることが必要になりました。
さらに、文字の大きさも10.5ポイントで記載することになりました。

 昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
昨今は、グローバル化や少子高齢化など社会のめまぐるしい変化に伴い、中小企業の経営課題も複雑化しており、中小企業だけでは処理しきれなくなってきています。
そのため、中小企業支援を行う支援事業の担い手の必要性が高まっています。
国は、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年に中小企業経営力強化支援法を施行しました。
この法律にもとづき、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
この認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識、支援に関する実務経験を持つ個人、法人、中小企業支援機関などを、経営革新等支援機関として認定しています。
この経営革新等支援機関を通じて、中小企業に対して専門性の高い支援を行うのです。
 事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。
事業者は以下の流れで経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
(1)経営課題を明確にする
まずはどんな課題が自社にあるのか明確にしなければ、経営革新等支援機関への相談すらままなりません。
あらかじめどんな相談をすべきかきちんと決めておきましょう。
(2)経営革新等支援機関を選定する
経営革新等支援機関は中小機構ホームページにある認定経営革新等支援機関検索システムで検索できます。
自社に近い場所にある認定経営革新等支援機関を選びましょう。
(3)経営革新等支援機関に相談する
経営革新等支援機関を選定したら、早速相談してみましょう。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
・経営状況の把握(財務分析、経営課題の抽出)
・事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
・事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言) 等
(4)事業計画を実現する
(5)モニタリング・フォローアップ
事業計画の実現後も定期的に巡回監査の実施や改善策の提案などのサポートを受けることができます。

































