 助成金申請に関する専門家と言えば、社会保険労務士です。
しかし、「助成金関係は対応しない」と言う社会保険労務士も多数います。
そうすると、一つの企業に対し、助成金関係はA社労士、労務関係はB社労士と言った構図が出来る場合があります。
もしA社労士とB社労士の意見が食い違うと、事業主が板挟みになってしまいます。
今回は、実例を交えて、そのケースの対処法について解説します。
助成金申請に関する専門家と言えば、社会保険労務士です。
しかし、「助成金関係は対応しない」と言う社会保険労務士も多数います。
そうすると、一つの企業に対し、助成金関係はA社労士、労務関係はB社労士と言った構図が出来る場合があります。
もしA社労士とB社労士の意見が食い違うと、事業主が板挟みになってしまいます。
今回は、実例を交えて、そのケースの対処法について解説します。
1.基本的に社会保険労務士同士でやり取りして調整します
「働き方改革助成金を受給するために就業規則を改定しようと思うのだけど」という事業主の依頼を受けて、助成金関係を担当するA社労士が新たな就業規則を作成しました。 そこに、労務関係を担当するB社労士から、就業規則に関して次のような質問がありました。 イ)「多様な正社員など」と言う表記が盛り込まれ、ずいぶん変わった就業規則になっているけど、どういう趣旨なのか? ロ)就業規則の内容がやけに簡略的だが、何か理由があるのか? ハ)「就業規則は従業員代表の意見を聴いて改定する」と書いてあるが、それ何故ですか? A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。
A社労士の回答は次のようなものです。
イ)「多様な正社員など」と言う表記を盛り込んだのは、助成金実施の際に、会社のみんなで話して決めた策です。
ロ)簡略的に見えても、書いてあること自体は間違っていません。足りない場合は、遠慮無く書き足してください。
ハ)「従業員代表の意見を…」の表現がなくても、労働基準法上意見を聴く義務がありますので、気になるならその表現は削除していただいても構いません。
また、A社労士はB社労士に「気になる点などは事業主様と話していただき、変えていただいて問題ありません。助成金が支給されない場合があるので、労働条件の不利益変更にだけはお気を付けください。」と補足しました。
このように、もし社労士によって意見の相違が出ても、社労士間でやり取りして調整するため、問題はありません。
2.社会保険労務士間でスムーズな連携が取れるようにしよう
「1人の社労士にだけ依存するのは心配だ」、「各分野に精通している社労士に依頼したい」などの理由で、担当の社会保険労務士が複数いる事業者は少なくないでしょう。 もし複数の社会保険労務士の関与が必要な案件があった場合は、その社会保険労務士間で密な連携が取れるようにしておきましょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆助成金・補助金に関する情報や記事を提供します!コンテンツプランはこちら!


 経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。
しかし、その計画を作成する目的が異なります。
経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。
中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。
申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。
一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。
人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。
このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。
しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。
 経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。
経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。
一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。
つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。
経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。
また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。
経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。
経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。
一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。
つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。
経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。
また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。
 経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。
経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。
一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。
どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。
ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。
(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。
(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。

 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
マンションアドバイザー制度を設けています。
マンションアドバイザー制度とは、建築士やマンション管理士などの専門家がマンションに訪問し、良好な維持管理への支援をしたり、建替えか改修かの判断を進める際のアドバイスをしたりする制度です。
東京都の自治体では、このマンションアドバイザー制度を利用したマンションの管理組合、区分所有者、賃貸マンションの所有者に対して、助成金を支給しているところもあります。
例として、東京都江戸川区のマンションアドバイザー制度利用助成を見てみましょう!
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターでは、
マンションアドバイザー制度を設けています。
マンションアドバイザー制度とは、建築士やマンション管理士などの専門家がマンションに訪問し、良好な維持管理への支援をしたり、建替えか改修かの判断を進める際のアドバイスをしたりする制度です。
東京都の自治体では、このマンションアドバイザー制度を利用したマンションの管理組合、区分所有者、賃貸マンションの所有者に対して、助成金を支給しているところもあります。
例として、東京都江戸川区のマンションアドバイザー制度利用助成を見てみましょう!


 就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
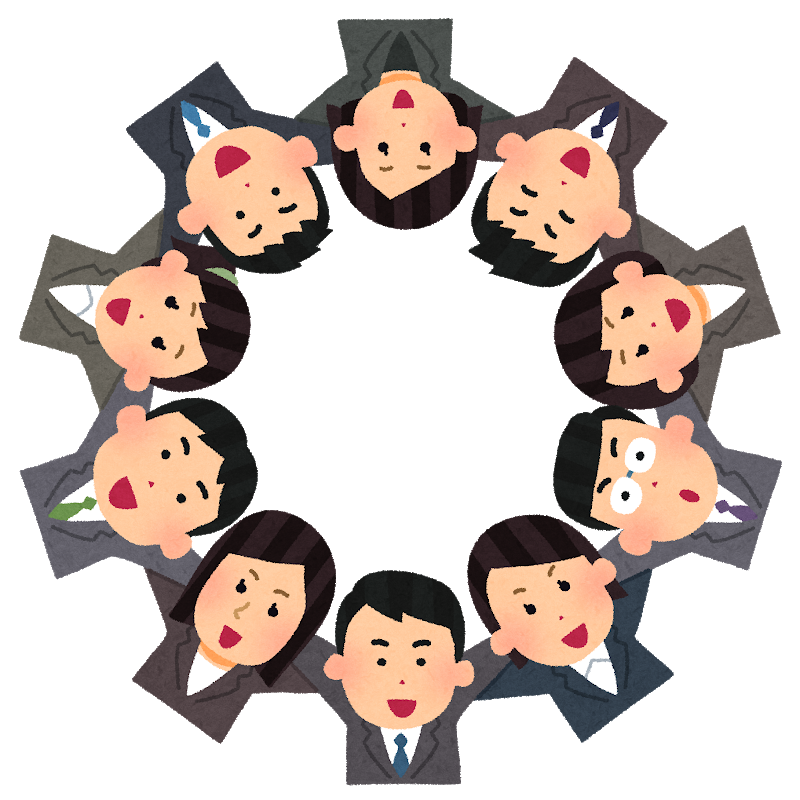 いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。

 「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」(社会保険労務士法第1条)
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づき、人材や労働、社会保険に関する諸問題に対処する役目を担う国家資格者です。
全国社会保険労務士連合会のホームページによると、社会保険労務士の主な業務は以下5つに分類されます。
★労働社会保険手続業務
★労務管理の相談指導業務
★年金相談業務
★裁判外紛争解決手続代理業務
★補佐人の業務
 労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更
労働社会保険に関する煩雑な手続きを代行します。
①労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
②各種助成金などの申請
③労働者名簿、賃金台帳の調製
④就業規則・労使協定(36協定)の作成、変更


 消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。
消費税が加算されている場合、報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、報酬分のみ源泉徴収を行います。
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
ちなみに、この考え方は交通費にも適用されます。



 4.助成対象外経費
公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
5.申請できる期間
申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請期間:
①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内
②毎年4月1日から定数に達するまで
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ・申請先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
アクセスマップ
電話3870-8400(直通)
4.助成対象外経費
公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
5.申請できる期間
申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請期間:
①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内
②毎年4月1日から定数に達するまで
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ・申請先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
アクセスマップ
電話3870-8400(直通)






























