 高齢社会が進行するにつれ、高齢者の労働力の活用が重要視されています。いつまでも働き続けられる制度の導入や高年齢者の働きやすい職場づくりが望まれています。
高齢労働者が定年を迎えても活躍できるように、政府は手厚くいろいろな制度を設けて支援しています。
今回は、60歳以上の高齢労働者に対して支給される厚生労働省の高年齢雇用継続給付についてご紹介します。
高齢社会が進行するにつれ、高齢者の労働力の活用が重要視されています。いつまでも働き続けられる制度の導入や高年齢者の働きやすい職場づくりが望まれています。
高齢労働者が定年を迎えても活躍できるように、政府は手厚くいろいろな制度を設けて支援しています。
今回は、60歳以上の高齢労働者に対して支給される厚生労働省の高年齢雇用継続給付についてご紹介します。
1.高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と、60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金に分かれます。 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上である、60歳以上65歳未満の一般被保険者が給付対象です。 60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満の場合に支給されます。2.支給額
(1)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合 各月の賃金の15%相当額が支給されます。 尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。 ※この額は毎年変更されます。 (2)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合 その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。 尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。 ※この額は毎年変更されます。
3.支給期間
(1)高年齢雇用継続基本給付金 支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。 (2)高年齢再就職給付金 支給対象期間は、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。 ただし、65歳に達する月が限度となります。4.まとめ
今回の給付金のように、高齢者の雇用に対して助成金を支給する制度は、官庁や自治体で多く公募されています。 また、高齢者であっても、若者以上のパフォーマンスを発揮できる方は多数いらっしゃいます。 「経験豊かな高齢者を雇いたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「高齢者」と検索してみてください。


 働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する制度です。
その教育訓練の中には、英語学習が入っており、英会話スクールが用意するコースを受講すれば、その受講料の一部が返ってくる仕組みです。
 以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
以下の主な条件を満たした上で、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・終了した在職者・離職者が対象となります。
①受講開始日現在で在職期間が通算3年以上であること
※初めて支給を受けようとする方については1年以上であること
※他の事業所などに雇用されていた期間も通算しますが、前職と現職の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
②受講開始日時点で在職者でない方は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること
※適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内
③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
※平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は適用されません。
 ①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円
①助成率
5分の1以内
②上限額と下限額
上限:10万円
下限:4,000円

 求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用へ移行した場合、助成金を支給します。
※この助成金は外国人労働者にも適用されます。
①助成対象者
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
2.紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
3.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
4.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
5.妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
6.就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
②助成額
対象者1人当たり月額最大4万円(最長3カ月間)
③募集期間
随時
 ②募集期間
随時
②募集期間
随時
 県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで
県内企業での外国人留学生インターンシップ受入を促進し、外国人留学生の県内就職増加につなげるため、外国人留学生によるインターンシップを受け入れた企業に対して、受入人数・日数に応じた補助金を支給します。
①補助対象経費
インターンシップ受入に係る事務経費
②補助額
外国人留学生1人につき5,000円(1日あたり)
※企業1社につき外国人留学生3人まで
※外国人留学生1人につき最大10日間 まで
③募集期間
インターンシップ実施2週間前まで

 失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
 ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
 ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。
ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。

 難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、継続就業に必要な支援を行う事業者に支給します。
 採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。
採用奨励金または雇用継続助成金の申請に加えて、対象労働者の雇入れ時または復職時に、治療と仕事の両立に配慮した勤務休暇制度などを新たに導入した場合、助成金を加算します。
ただし、採用奨励金は、平成30年1月1日以降にハローワークから紹介を受けて対象労働者を雇い入れた場合に限ります。










 ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。
支給額
雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給
第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円
第2期(第1期後~6ヵ月):30万円
※上記支給額は中小企業の場合
上記の以外にも「支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない」など細かな要件があります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などに定めていることが必要です。
支給額
雇入れから1年間を支給対象期間として、合計最大60万円が支給
第1期(雇入れ~6ヵ月):30万円
第2期(第1期後~6ヵ月):30万円
※上記支給額は中小企業の場合
上記の以外にも「支給対象期間の途中で対象労働者が定年に達する場合は支給対象とならない」など細かな要件があります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の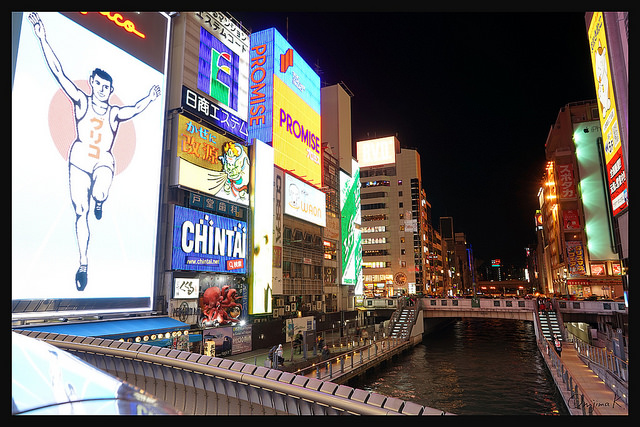
 実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に
キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを
お願いしたのですが、
その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、
結局申請できなかったと言う過去がありました。
お金の話で汚いかもしれませんが、
その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を
相当ケチってしまっていたのです。
助成金のために雇用契約書を整備しようとしても
A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。
事業主としても、
雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、
時間だけが過ぎていました。
書類に判子は一切押していないのに、
事業主としては、
「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」
と思っていたようです。
助成金の取得には、
きちんと法律通りに労務管理等ができている、
環境が整っている必要があります。
まだの場合はその整備が先です。
それを外部の業者にお願いするのですから、
過度に値切ったりしますと、
悪循環に陥っていきます。ご注意ください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に
キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを
お願いしたのですが、
その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、
結局申請できなかったと言う過去がありました。
お金の話で汚いかもしれませんが、
その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を
相当ケチってしまっていたのです。
助成金のために雇用契約書を整備しようとしても
A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。
事業主としても、
雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、
時間だけが過ぎていました。
書類に判子は一切押していないのに、
事業主としては、
「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」
と思っていたようです。
助成金の取得には、
きちんと法律通りに労務管理等ができている、
環境が整っている必要があります。
まだの場合はその整備が先です。
それを外部の業者にお願いするのですから、
過度に値切ったりしますと、
悪循環に陥っていきます。ご注意ください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 2.規定を設ける必要なし?
現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、
特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。
この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。
例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、
実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、
該当する規定を設けることが必要となります。
しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、
アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。
その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。
訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。
そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。
この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、
現在のところ予定されていません。
また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、
この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。
そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、
支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。
せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
2.規定を設ける必要なし?
現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、
特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。
この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。
例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、
実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、
該当する規定を設けることが必要となります。
しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、
アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。
その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。
訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。
そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。
この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、
現在のところ予定されていません。
また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、
この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。
そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、
支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。
せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

 【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】
【対象となる企業】
上記の対象者をハローワーク・地方運輸局・特定地方公共団体・職業紹介事業者のいずれかからの紹介によって、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する事業主。
※継続して雇用する労働者……対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あることをいいます。
※雇い入れた労働者に対する配慮事項……2016年4月より施行された『障害者差別解消法』によって、事業主には過度な負担にならない程度で『合理的配慮の提供』が義務付けられています。具体的には以下のようなものです。
(例1)口頭での指示理解が困難な従業員に、写真や図を用いた文書を渡す
(例2)車いすを利用する従業員に、机の高さや作業スペースを調節する など
【助成額】


 3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。
3.離職者に関する書類を提出する際の注意点
直近の例では、ある助成金の支給申請時に、
「雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」
と言われたものがあります。
これは、雇用保険の被保険者が会社を辞めるとき、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を提出します。
その書類の中に、「喪失原因」という欄があり、それはすなわち会社を辞めた理由です。
ただこれがわかりにくい書き方になっているのです。その欄は、次の3つから選びます。
1.離職以外の原因
2.3以外の原因
3.事業主の都合による離職
確かにわかりにくいですね。
「1」は、被保険者の死亡などです。
「2」はいわゆる自己都合退職がほとんど。
「3」が今回の話題の会社都合の離職です。
その会社では、確かに会社都合の退職などは出ていませんでした。しかしこのわかりにくい表記によって、間違って「3」を選んでいたのです。
今回は本当に間違えでしたので、それを訂正し、その後書類を再提出で無事に受理されました。
しかし、もしこれが本当に会社都合の離職で、それを助成金欲しさに訂正したとなれば大問題です。当然不正受給ということになります。
また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。
そうすると、その「会社都合」が嘘ということで、こんどはそっちで問題が生じます。
みなさん、離職の際の書類にはくれぐれもご注意ください。


 3.NG例
この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか?
「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」
支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。
では、今回のケースはどうでしょう?
「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。
前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。
後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。
対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。
該当する方は大いに制度をご活用ください!
3.NG例
この助成金に関して実際あった質問例ですが、皆さんはどう思われますでしょうか?
「この前、うちの店(リラクゼーションの店)に見学に来た人が、『ぜひ応募したい』と言うのです。なので、『ハローワークから応募してください』と言いました。これでハローワークを経由してもらったので、当然助成金の対象になりますよね?」
支給要件の中に次のような文言があります。「以下のいずれにも該当しないこと」と書かれていて、18個の要件が書かれています。その中に、「ハローワーク等の紹介以前に雇用の約束があった労働者を雇入れる場合」とあります。
では、今回のケースはどうでしょう?
「是非うちで一緒にがんばりましょう!」という感じだったのか、それとも、「今ハローワークに求人を出しているので、それを見てうちで良かったら応募してみてください。あとは面接で話しましょう。」という感じだったのか。その辺の状況によります。つまり実態で判断することになります。
前者の場合はシナリオが出来ていて、明らかにお金目的ですね。不正受給と見なされることもあります。
後者でも内容によってはOUTでしょう。例えば、見学者が来てからハローワークに求人を慌てて出して採用させるなどはNGとなります。
対象になるケースとしていちばんわかりやすいのは、「見ず知らずの人がハローワークで求人を見て応募してくる。その人がたまたま母子家庭だった」というケースです。なんとなくイメージは伝わりますでしょうか。
該当する方は大いに制度をご活用ください!

 3.高齢者や障害者を雇用したら
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。
①短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:240万円(100万円)
②短時間労働者(※2)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。
ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。
雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。
3.高齢者や障害者を雇用したら
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
こちらも日本人だけでなく、外国人労働者も対象になります。
①短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※1)
支給額:240万円(100万円)
②短時間労働者(※2)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給額:40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円(30万円)
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
外国人労働者を雇用する際は、是非上記の助成金を検討してみてください。
ただし、その外国人に在留資格があるのかは、必ずチェックしておきましょう。「雇ったら実は不法入国者でした」などと言う場合、最悪雇った側も罰せられる可能性があります。
雇用する前に、パスポート、就労資格証明書、外国人登録証明書などを見せてもらい、雇っても問題ない人物かどうか確認しましょう。

 2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには?
今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。
ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。
その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。
よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。
同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。
そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。
そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。
そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。
今から2ヶ月前というと、7月ですね。
2.国だけでなく東京都の助成金も支給されるには?
今回はその「有期雇用→正社員」の例で紹介致します。
ちなみに、国への支給申請は、正社員転換後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、20日締め当月25日払いの会社だとします。有期契約から正社員に転換し、今年8月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は8月25日に支給されますね。その翌日から2ヶ月以内に国への支給申請が可能です。
その申請を済ませて、さらにそこ(国への支給申請日)から2ヶ月以内に東京都への支給申請を済ませれば、東京都からの助成金の対象にもなります。
よって、このケースですと、8月26日から9月29日までの約1ヶ月の間に、国→都の順で提出が必要となります。
同じく有期契約から正社員への転換で、9月20日に正社員として6ヶ月を経過したとします。その賃金は9月25日に支給されますね。
そんな場合は、9月26日から9月29日までの4日間に、国→都の順で提出が必要となります。これは大変ですね。
そのため、後者では今のうちにある程度の準備をしておく必要があります。案外、この後者の例、つまりぎりぎりのケースも結構あるのではないでしょうか。
そして、正社員としての6ヶ月分の賃金支給日が9月29日以降の方、残念ながら東京都の支給申請日は間に合いません。急ぐことなく国への提出書類をご用意ください。
今から2ヶ月前というと、7月ですね。

 では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。
厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。
では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。
厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。



 ※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。

 3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円
②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。
3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円
②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。

 本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!
本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
是非、ご活用下さい!


































