今回は助成金・補助金に関する疑問に回答します!

今回のテーマ ちゃんとしたコンサルタント会社の見分け方とは?
1.こんなコンサルタント会社は要注意?
コンサルタント会社による助成金関係のセールス自体は珍しいことではありません。 しかし、その中には、あたかも「厚生労働省からの電話である」と誤解しやすいように、うまくしゃべっている悪質な企業もあります。 厚生労働省からの電話は基本的にありません。 このような悪質なコンサルタント会社には、以下のような特徴があります。 ①コンサルタント会社の担当者が助成金をよく理解していない為、そのまま進めていたら本来受給可能な助成金が、実施不可能になっていた。 ②助成金を数多く紹介することにより、獲得金額を多く見せることばかりが説明の中心になっている。 ③そもそも助成金は、労働関係諸法令を守っていなければ支給されないことは何の説明もなく、社労士が登場して初めてそれがわかる事が多い。 助成金のセールスを受けて、「数百万もらえるかも」とテンションが上がっている事業主も少なくないでしょうが、そのセールス内容がはたして正当なものかどうか吟味する必要があります。2.きちんとしたコンサルタント会社の判断基準とは?
コンサルタント会社などが、助成金というものを世に知らしめる事自体は、法に触れない限りは問題ではありません。 ただ、助成金は 「社労士やコンサル会社に頼めば獲得できるという単純なものではない。事業主と担当社労士の間で十分な情報提供や共有がなされ、一つ一つ丁寧に判断していくことが必要だ。」 と考えることが基本です。 そのことをきちんと理解しているかどうか?それがきちんとしたコンサルタント会社かどうかの判断基準になります。 そのきちんとしたコンサルタント会社に社労士を紹介してもらって、その上で実施の方向に進んでいくのであれば、大丈夫でしょう。 ☆助成金なうはこちら! ☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら! ☆御社のニーズに合った助成金・補助金情報を提供します!マイプラン契約はこちら! ☆過去の助成金セミナーをお手頃価格で視聴できる!セミナービデオの購入はこちらから!






 ただし、B型の場合は、年平均5%の投資利益率(営業利益+減価償却費の増加額を設備投資額で除したもの)が求められます。
その根拠を会計士もしくは税理士が確認した後、経済産業省にB型確認書を提出します。
B型確認書が認められた場合は、経営力向上計画にB型の確認番号を記載し、関係省庁に提出という流れになるため、A型と比べて時間がかかります。
また、投資利益率の向上のための根拠を示すために、現状の機械設備により稼働率や不良率、売上、利益の数値及び根拠データや書面の提出が求められるため、A型よりハードルは高くなっています。
経営力向上計画を作成して優遇を受けるには、A型の申請書を提出できるよう、工業会の証明書をもらった方がよさそうですね。
ただし、B型の場合は、年平均5%の投資利益率(営業利益+減価償却費の増加額を設備投資額で除したもの)が求められます。
その根拠を会計士もしくは税理士が確認した後、経済産業省にB型確認書を提出します。
B型確認書が認められた場合は、経営力向上計画にB型の確認番号を記載し、関係省庁に提出という流れになるため、A型と比べて時間がかかります。
また、投資利益率の向上のための根拠を示すために、現状の機械設備により稼働率や不良率、売上、利益の数値及び根拠データや書面の提出が求められるため、A型よりハードルは高くなっています。
経営力向上計画を作成して優遇を受けるには、A型の申請書を提出できるよう、工業会の証明書をもらった方がよさそうですね。














 当然捨ててしまったものは返ってきませんので、「以後決められたとおり保存します」という旨の書面を提出して、これにてその勧告に関することは終了となりました。
しかし、ちょうどその是正勧告を受けたとき、キャリアアップ助成金の支給申請が控えていました。もちろん是正勧告止まりで、その内容については改善をしたので、何ら問題はなく支給申請できます。
ですが、もしこれが2回目や3回目の是正勧告となると、是正勧告では収まらず、書類送検なんて言うこともあります。そうなるとしばらく支給申請は出来ません。
また、是正勧告の回数にかかわらず、ことが大きければいきなり書類送検される可能性もあります。
やはり助成金の支給申請をしたければ、ちゃんと労働関係の諸法令を守らなければいけませんね。
誤解を恐れずに言えば、助成金ありきの企業ほど、その環境が整っていない、つまり労働関係の諸法令に違反しているケースが多く見られます。もちろんそのままでは、申請は出来ません。
「申請するにはまず環境を整えてから!」と言うことを念頭に置きながら、助成金獲得を目指してみてください。
当然捨ててしまったものは返ってきませんので、「以後決められたとおり保存します」という旨の書面を提出して、これにてその勧告に関することは終了となりました。
しかし、ちょうどその是正勧告を受けたとき、キャリアアップ助成金の支給申請が控えていました。もちろん是正勧告止まりで、その内容については改善をしたので、何ら問題はなく支給申請できます。
ですが、もしこれが2回目や3回目の是正勧告となると、是正勧告では収まらず、書類送検なんて言うこともあります。そうなるとしばらく支給申請は出来ません。
また、是正勧告の回数にかかわらず、ことが大きければいきなり書類送検される可能性もあります。
やはり助成金の支給申請をしたければ、ちゃんと労働関係の諸法令を守らなければいけませんね。
誤解を恐れずに言えば、助成金ありきの企業ほど、その環境が整っていない、つまり労働関係の諸法令に違反しているケースが多く見られます。もちろんそのままでは、申請は出来ません。
「申請するにはまず環境を整えてから!」と言うことを念頭に置きながら、助成金獲得を目指してみてください。


 そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。
そんな話をしますと、時々聞くのが、
「いや、この前○○から聞いたけど、2,3か月でもらえるのがあった」
といわれたりします。
これは「助成金」ではなく、「補助金」であることが多いです。
「助成金」は厚生労働省管轄で、人の雇用に関連するものです。
それに対し「補助金」は中小企業庁や区市町村の管轄が基本的で、経費に対して補填されるイメージのものです。
目的でだけではなく支給元や目的など、両者は根本的に違います。
最近では、採択が難しい「補助金」よりも、要件を満たしていれば支給される「助成金」にシフトチェンジする傾向が見受けられます。
ですが「補助金」の感覚で「助成金」に取り組むことは出来ません。
さらにそれがわかると、
「いやー、資金繰りが苦しくなる○月に支給されるの探してよ!」
と言われたりします。
助成金はそもそもそういう性質ではないのですね。
気持ちはわかりますが、国は助成金を会社の資金繰りに使うという状況を想定していません。
逆に、資金繰りなどの目的を捨てて、会社の労務廻りの整備に使うお金にする発想に切り替えられた企業が、結果として多くの助成金の機会を得ています。

 2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。
2.パンフレット等の用語が非常に分かりづらい
次に、パンフレット等の用語ですが、実は雇用関係助成金は、「雇用保険法」という法律が根拠となっています。
そのため、パンフレット等も、法律用語がたくさん登場します。
下記に例を挙げてみますね。
「育児・介護休業法第2条第1号に規定する、育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること」
正直「?」という方が大半だと思います。「育児介護休業法?」、「労働協約?」となるのが普通です。
このような書き方が非常に多いのです。
それが自社にとって重要な要件でなければスルーしても問題になりませんが、そうでない場合には、致命傷になったりします。
3.申請するなら専門家に頼みましょう!
ということで、雇用関係助成金を申請するのであれば、自社で確認をするか、専門家に頼むか、どちらがいいのでしょう?
当然、後者の方が精度が上がり、楽なのは言うまでもありません。
専門家に頼むとお金がかかる、と言うことで自社でやってみるという方も案外いらっしゃいます。
ですが、制度が下がり、せっかく時間をかけて、策を講じても、不支給や受給不可となってはかえってマイナスです。
専門家に頼んで多少手元に残る金額が減ったとしても、受給できることによりマイナスにはならないのであれば、やはりプロに頼むのがいちばんです。
案外プロに頼む方が、時間と効果を考えると安上がりだったりします。


 この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。
その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。
今更どうやってももらえません。
そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。
正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。
一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。
ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。
誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。
大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
この助成金は、育休(通常はその前の産休)に入る前から、仕事の引き継ぎや上司との面談、育児介護休業規程などを整えたりしなければいけません。
その企業様は、コンサルタント会社から情報をもらい、その時に「育休から復帰してからの申請でももらえますよ」と言われて信じてしまったそうです。
今更どうやってももらえません。
そのコンサルタント会社のことは知り得ませんので、何ともいえません。
正確な情報を伝えたけど、企業様が勘違いしていたと言うこともあるでしょう。
一方で、そのコンサルタント会社が間違っていたと言うこともあり得るでしょう。
ただ、日頃から助成金に携わる立場からいえることは、コンサルタント会社からもらった情報を頼りにして、結果として受給できるはずの助成金が受給不可能となっているケースが後を絶たないということです。
誤解があってはいけないので付け加えますが、コンサルタント会社のすべてがそうだとは思っていません。きちんとした会社であり、社会保険労務士も存在していて、問題のないコンサルタント会社もちゃんとあります。
大丈夫なコンサルタント会社かどうかの見極め方は一概には言えませんが、少なくとも社労士という専門家が存在しているかどうかが、一つの見極め方となるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 2次公募に関しては、1次の採択者数が9千以上あったことで採択枠は少なくなることが予想され、また、1次の動向を見て先端設備の承認を受ける企業が標準化されることが予想され、かなりの激戦になることは必至かと思われます。
さらに中国地方での被災により、中国地方の企業が優先採択されるため、他の地域は採択されるのはかなり狭き門になるでしょう。
2次に公募される場合は、できるだけ多くの加点要素を取ることをお奨めします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
2次公募に関しては、1次の採択者数が9千以上あったことで採択枠は少なくなることが予想され、また、1次の動向を見て先端設備の承認を受ける企業が標準化されることが予想され、かなりの激戦になることは必至かと思われます。
さらに中国地方での被災により、中国地方の企業が優先採択されるため、他の地域は採択されるのはかなり狭き門になるでしょう。
2次に公募される場合は、できるだけ多くの加点要素を取ることをお奨めします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 その企業様としては、残業代は払っている認識だったのです。
もしかして、K先生は、その残業代は「その他手当」にある「月によって支給されている2~4万円」に当たるのではと思い、企業様に聞いてみると、「そうですよ!」とのことでした。正直適当だったのです。
正しいルールをご存じの方は、これが間違えであることはおわかりでしょう。みなし残業代とか名称の問題ではなく、残業した時間分に応じて支給されなければいけません。
仮にそのみなし残業代が10時間分で、その月に15時間の残業をした場合は、さらに5時間分を支給しなければいけません。この解釈が無かったのです。
その後K先生が丁寧に説明をし、未払い分を精算してから支給申請をするか、今回は申請を諦めるか、二者択一で「今回は諦める」となりました。
その後、未払い残業代がどうなったかは気になりますが、その企業様との契約の関係上、それ以上の深入りはできませんでした。
皆さんも、助成金を目指す際は、一度専門家に診断をしてもらうと良いかと思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
その企業様としては、残業代は払っている認識だったのです。
もしかして、K先生は、その残業代は「その他手当」にある「月によって支給されている2~4万円」に当たるのではと思い、企業様に聞いてみると、「そうですよ!」とのことでした。正直適当だったのです。
正しいルールをご存じの方は、これが間違えであることはおわかりでしょう。みなし残業代とか名称の問題ではなく、残業した時間分に応じて支給されなければいけません。
仮にそのみなし残業代が10時間分で、その月に15時間の残業をした場合は、さらに5時間分を支給しなければいけません。この解釈が無かったのです。
その後K先生が丁寧に説明をし、未払い分を精算してから支給申請をするか、今回は申請を諦めるか、二者択一で「今回は諦める」となりました。
その後、未払い残業代がどうなったかは気になりますが、その企業様との契約の関係上、それ以上の深入りはできませんでした。
皆さんも、助成金を目指す際は、一度専門家に診断をしてもらうと良いかと思います。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
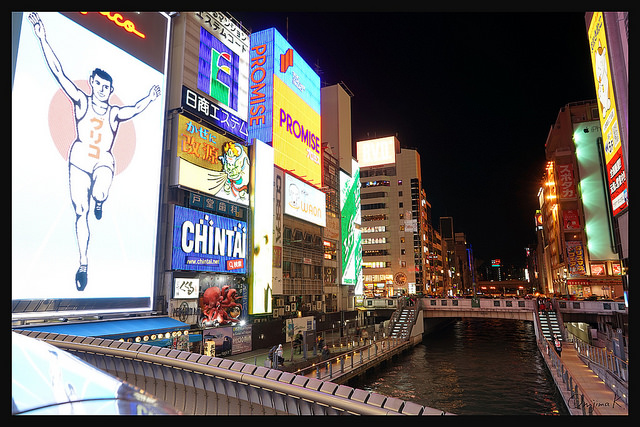
 実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に
キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを
お願いしたのですが、
その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、
結局申請できなかったと言う過去がありました。
お金の話で汚いかもしれませんが、
その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を
相当ケチってしまっていたのです。
助成金のために雇用契約書を整備しようとしても
A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。
事業主としても、
雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、
時間だけが過ぎていました。
書類に判子は一切押していないのに、
事業主としては、
「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」
と思っていたようです。
助成金の取得には、
きちんと法律通りに労務管理等ができている、
環境が整っている必要があります。
まだの場合はその整備が先です。
それを外部の業者にお願いするのですから、
過度に値切ったりしますと、
悪循環に陥っていきます。ご注意ください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に
キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを
お願いしたのですが、
その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、
結局申請できなかったと言う過去がありました。
お金の話で汚いかもしれませんが、
その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を
相当ケチってしまっていたのです。
助成金のために雇用契約書を整備しようとしても
A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。
事業主としても、
雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、
時間だけが過ぎていました。
書類に判子は一切押していないのに、
事業主としては、
「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」
と思っていたようです。
助成金の取得には、
きちんと法律通りに労務管理等ができている、
環境が整っている必要があります。
まだの場合はその整備が先です。
それを外部の業者にお願いするのですから、
過度に値切ったりしますと、
悪循環に陥っていきます。ご注意ください。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 つまり、着手金を請求してくる専門家は、
助成金獲得に向けての経験値、
本気度が高いケースが多いのです。
着手金の重要性を判っている。
だからこそ請求してくるのです。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、
着手金の扱いをどうするのか。
そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。
後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や
「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」
などです。
また最近では、
着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、
「助成金専用顧問」のような形をとり、
毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、
着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、
「単に専門家に頼んだら獲得できる」
というイメージではなく、実際は、
「その為の環境が整っていないと獲得できない」
ということに、気がつき始めた企業が多いことが
背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、
専門家に頼むことが、
案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
つまり、着手金を請求してくる専門家は、
助成金獲得に向けての経験値、
本気度が高いケースが多いのです。
着手金の重要性を判っている。
だからこそ請求してくるのです。
ただし、万が一助成金獲得ができない場合、
着手金の扱いをどうするのか。
そこだけは決めておいたほうが宜しいかと思います。
後に揉めないためです。
例えば、「着手金は返金しない」や
「社労士等の明らかなミスの場合は返金する」
などです。
また最近では、
着手金や成功報酬と言ったやり方ではなく、
「助成金専用顧問」のような形をとり、
毎月いくらかを支払う(いただく)代わりに、
着手金や成功報酬をなくすケースも増えてきています。
この現象は、助成金受給は、
「単に専門家に頼んだら獲得できる」
というイメージではなく、実際は、
「その為の環境が整っていないと獲得できない」
ということに、気がつき始めた企業が多いことが
背景としてあります。
そんな社内の諸整備も含めて、
専門家に頼むことが、
案外助成金獲得の近道で安上がりだったりします。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 例えば、国であれば、
客室や共用部の改修のための
①「宿泊施設のバリアフリー化促進事業」(上限500万円)
館内案内表示の多言語化やトイレの洋式化、
無線LAN設置等のための
②「宿泊施設インバウンド対応支援」(上限100万円)
などがあります。
東京都であれば、
分煙のための設備導入による
①「分煙環境整備補助金」(上限300万円)
旅館を中心とした地域グループが実施する
旅館ブランドの構築に向けた新たな取組
②「TOKYO旅館ブランド構築・発信事業」(上限1000万円)
③「宿泊施設バリアフリー化支援補助金」(上限3000万円)
クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入、
テレビの国際放送設備等による
④「インバウンド対応力強化支援補助金」(上限300万円)
などがあります。
また、市区町村においても、様々な補助金や助成金が出ています。
補助金の場合は、
公募の時期が限られていますので、
国(観光庁、中小企業庁)、
都道府県、市区町村から
発信される情報については
常にウオッチしていくことが
補助金を獲得する上で重要になります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
例えば、国であれば、
客室や共用部の改修のための
①「宿泊施設のバリアフリー化促進事業」(上限500万円)
館内案内表示の多言語化やトイレの洋式化、
無線LAN設置等のための
②「宿泊施設インバウンド対応支援」(上限100万円)
などがあります。
東京都であれば、
分煙のための設備導入による
①「分煙環境整備補助金」(上限300万円)
旅館を中心とした地域グループが実施する
旅館ブランドの構築に向けた新たな取組
②「TOKYO旅館ブランド構築・発信事業」(上限1000万円)
③「宿泊施設バリアフリー化支援補助金」(上限3000万円)
クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入、
テレビの国際放送設備等による
④「インバウンド対応力強化支援補助金」(上限300万円)
などがあります。
また、市区町村においても、様々な補助金や助成金が出ています。
補助金の場合は、
公募の時期が限られていますので、
国(観光庁、中小企業庁)、
都道府県、市区町村から
発信される情報については
常にウオッチしていくことが
補助金を獲得する上で重要になります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 補助金が少額の場合は、
自己資金ですべて賄うということでもよいと思いますが、
補助額が1千万以上である場合は、
仮に自己資金が潤沢であっても借入で、
ある程度賄うほうが印象がよくなります。
補助金の目的の一つに金融機関の貸出先を
供給する面があります。
したがって、つなぎ融資を使うことで
補助期間をスムーズに推進させることを訴求します。
また、あまりにも内部留保が多い場合、
何らかの理由があるはずですので、
そうした理由も書くようにすると説得力が上がるでしょう。
資金調達方法と同様に、
申請する補助金がなぜ必要なのか
ということも明記してください。
事業を推進するためには、
補助事業の必要性も力説することで、
説得性を高める必要があります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
補助金が少額の場合は、
自己資金ですべて賄うということでもよいと思いますが、
補助額が1千万以上である場合は、
仮に自己資金が潤沢であっても借入で、
ある程度賄うほうが印象がよくなります。
補助金の目的の一つに金融機関の貸出先を
供給する面があります。
したがって、つなぎ融資を使うことで
補助期間をスムーズに推進させることを訴求します。
また、あまりにも内部留保が多い場合、
何らかの理由があるはずですので、
そうした理由も書くようにすると説得力が上がるでしょう。
資金調達方法と同様に、
申請する補助金がなぜ必要なのか
ということも明記してください。
事業を推進するためには、
補助事業の必要性も力説することで、
説得性を高める必要があります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
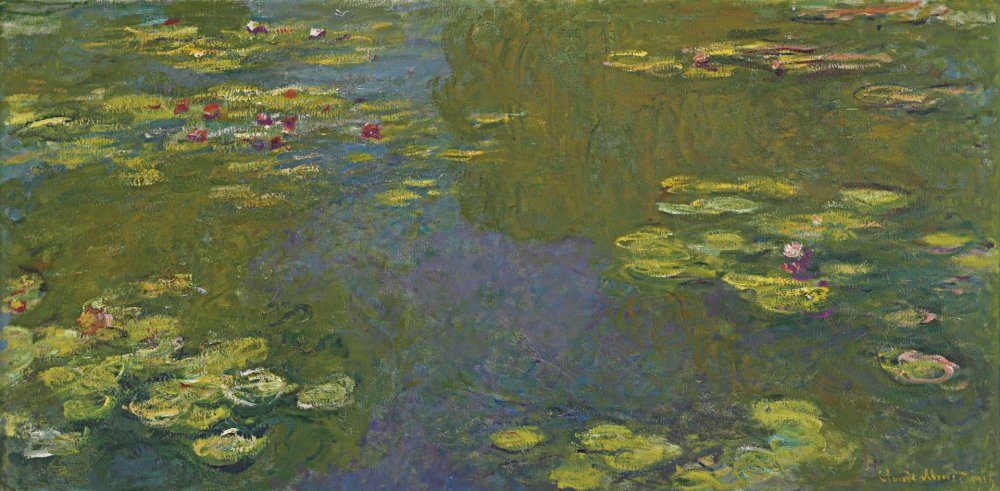 主な要件や内容は、次の通りです。
【主な要件(一部抜粋)】
平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。
交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。
※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。
平成29年度の東京都正規雇用等転換促進助成金から支給決定を受けている同一の労働者ではないこと。
3か月間の支援期間(後述します)終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援期間の末日において都内事務所に在籍していること。
支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。
【支援事業の実施】
申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。
①3年間の指導育成計画の策定
②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
③指導育成計画に基づく研修の実施
上記のように、ややこしくなりました。
【受給額】
1人につき20万円で、3人以上は何人でも60万円で打ち止め、
つまり上限60万円ということになります。
上記にプラスして、退職金制度を新たに整備した場合、
1申請につき10万円を加算してもらえます。
昨年度までと比べると、減額され縮小もされました。応募方法も時期が設けられています。
いずれにしても、国(東京労働局)からの支給決定があってから、ようやく手続きが可能となります。平成29年4月以降正社員転換済みで、国からの支給決定が既にあった企業様は、今のうちに諸条件を確認し、応募を検討されてみてはいかがでしょうか。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
主な要件や内容は、次の通りです。
【主な要件(一部抜粋)】
平成29年4月1日以降に支給対象労働者を転換等し、東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定をしていること。
交付申請日時点で、上記正社員化コースで転換等した支給対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。
※支援とは、下記【支援事業の実施及び退職金制度整備】における支援事業のことをいいます。
平成29年度の東京都正規雇用等転換促進助成金から支給決定を受けている同一の労働者ではないこと。
3か月間の支援期間(後述します)終了日において、同一の事業主との間で転換又は直接雇用後の雇用区分の状態が1年以上継続し、支援期間の末日において都内事務所に在籍していること。
支援期間の末日において有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。
【支援事業の実施】
申請事業主は、支給対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと。
①3年間の指導育成計画の策定
②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
③指導育成計画に基づく研修の実施
上記のように、ややこしくなりました。
【受給額】
1人につき20万円で、3人以上は何人でも60万円で打ち止め、
つまり上限60万円ということになります。
上記にプラスして、退職金制度を新たに整備した場合、
1申請につき10万円を加算してもらえます。
昨年度までと比べると、減額され縮小もされました。応募方法も時期が設けられています。
いずれにしても、国(東京労働局)からの支給決定があってから、ようやく手続きが可能となります。平成29年4月以降正社員転換済みで、国からの支給決定が既にあった企業様は、今のうちに諸条件を確認し、応募を検討されてみてはいかがでしょうか。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

 それに対して、国の補助金の場合、
申請段階で総額が決まりますが、
それほど厳密な購入先の情報は求められません。
また、国の補助金は書類不備だと落とされますが、
都道府県の場合は、提出時に書類不備等を指摘してくれる場合が多いため、
形式上より内容に比重が置かれているということになります。
もちろん、申請書を出す総人数が国の場合は多いため、
きめ細かい対応を一社ごとに行えないという実情もあるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
それに対して、国の補助金の場合、
申請段階で総額が決まりますが、
それほど厳密な購入先の情報は求められません。
また、国の補助金は書類不備だと落とされますが、
都道府県の場合は、提出時に書類不備等を指摘してくれる場合が多いため、
形式上より内容に比重が置かれているということになります。
もちろん、申請書を出す総人数が国の場合は多いため、
きめ細かい対応を一社ごとに行えないという実情もあるでしょう。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
 最も必要なのは、
まずその対象となる企業が
どのような企業なのかを知ることなのです。
例えば、全員が正社員であるなら、
何か研修をする予定があるか等を聞きながら、
「それならば〇〇研修助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」
といった感じで進めていきます。
そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。
その為、
初対面で「簡単に取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、
「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
最も必要なのは、
まずその対象となる企業が
どのような企業なのかを知ることなのです。
例えば、全員が正社員であるなら、
何か研修をする予定があるか等を聞きながら、
「それならば〇〇研修助成金が可能性としてあります。その研修はどなたを対象とするものですか?」
といった感じで進めていきます。
そうすることで、「これなら助成金対象になりそうですね」とか、「今回は対象外ですね」などと見えてくるのです。
その為、
初対面で「簡単に取れそうな助成金はありますか?」と質問されても、
「御社の事情を色々とお聞かせいただき、その上で見つけられるものです。」と答えるしかないのです。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の

 3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、
報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、
報酬分のみ源泉徴収を行いますが、
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、
10.21%となります。
100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、
100万円と残り50万円を分けて計算し、
100万円に対しては10.21%なので102,100円、
残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、
あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の
3.消費税と報酬の区分について
消費税が加算されている場合、
報酬と消費税が明確に区分されているのであれば、
報酬分のみ源泉徴収を行いますが、
区分されていない場合はまとめて源泉徴収されます。
これは交通費も同様の考え方になります。
4.源泉徴収額の割合について
具体的な源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合、
10.21%となります。
100万円を超える部分に関しては、20.42%となります。
例えば150万円の報酬だった場合、
100万円と残り50万円を分けて計算し、
100万円に対しては10.21%なので102,100円、
残り50万円に対しては20.42%のため102,100円、
あわせて204.200円の源泉徴収額となります。
☆早い者勝ち!助成金・補助金の





























