助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスを
開始致しました!
 今回のテーマ
大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます!
1.中退者・既卒者は今でも就職が難しい
高校中退者の方でも、会社を立ち上げたり大企業で出世したりなど、ビジネス界で活躍する方は少なくありません。しかし、現在でも高校中退者が就職する機会は非常に限られています。
また、大学中退者・既卒者の方も、新卒重視の傾向がまだ根強い為、就職することがなかなか難しい状況となっています。
そこで、厚生労働省では、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)を設けています。
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
2.主な支給要件
この助成金の支給要件は、以下のコースに分かれます。
【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
今回のテーマ
大学既卒者や高校中退者の採用に助成金が出ます!
1.中退者・既卒者は今でも就職が難しい
高校中退者の方でも、会社を立ち上げたり大企業で出世したりなど、ビジネス界で活躍する方は少なくありません。しかし、現在でも高校中退者が就職する機会は非常に限られています。
また、大学中退者・既卒者の方も、新卒重視の傾向がまだ根強い為、就職することがなかなか難しい状況となっています。
そこで、厚生労働省では、学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)を設けています。
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。(平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
2.主な支給要件
この助成金の支給要件は、以下のコースに分かれます。
【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者の通常の労働者(※2)として雇用したこと(卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要)
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
 3.助成金の支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。
3.助成金の支給額
対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、以下の金額が支給されます。
 ※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください!
助成金なうで「既卒者」を検索!
☆申請コンサルタントはこちらから☆
※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
既卒者や中退者の採用をお考えの方は是非この助成金を御検討になってください!
助成金なうで「既卒者」を検索!
☆申請コンサルタントはこちらから☆
-
-
キーワード検索
-
直近1週間の人気記事ランキングBest10
直近10回分の投稿
 5/11(火)新規公示案件情報
5/11(火)新規公示案件情報 5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】
5/11(火)新規公示案件情報【有料会員限定】 助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様
助成金なう採用事例 ファイナンシャルアライアンスFP黒川事務所 様 令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか?
令和3年度の両立支援等助成金の各コースはどうなりますか? 展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など
展示会の助成金まとめ 国内外出展/オンライン出展/キャンセル料/PR活動 など 祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪
祝、会員10万人突破!小冊子「個人で使える助成金のすすめ」先着1000人にプレゼント♪ 小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!!
小冊子「個人で使える助成金のすすめ」2021年春版登場!! 事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】
事業再構築補助金セミナー 5月10日2次公募開始/緊急事態宣言枠は3/4補助【9期100社限定セミナー募集】 スズメバチの駆除で出る助成金とは?
スズメバチの駆除で出る助成金とは? 中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?
中小企業庁の補助金申請に必要!GビズIDとは?
カテゴリー
カレンダー
2025年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 アーカイブ
タグ一覧



 4.助成額
工事費用の2分の1とし、10万円を上限とする。
※工事費用には、設備購入費用を含みます。
5.申請方法
環境保全課窓口で配布する申請書に必要書類と印鑑(書類に不備があれば使用)をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。
※必ず機器の設置前に申請してください。
※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。
6.申請期間
6月30日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで
※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
4.助成額
工事費用の2分の1とし、10万円を上限とする。
※工事費用には、設備購入費用を含みます。
5.申請方法
環境保全課窓口で配布する申請書に必要書類と印鑑(書類に不備があれば使用)をご持参(郵送は不可)の上、環境保全課窓口で申請をお願いします。申請書類等は、市のホームページからダウンロードも可能です。
※必ず機器の設置前に申請してください。
※助成金の交付決定後に工事開始となります。申請から交付決定まで、通常10日程度かかりますので、余裕を持って申請をお願いします。
6.申請期間
6月30日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで
※申請期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。





 政府は、人工知能(AI)やロボット、医療・介護サービスなどの最先端技術を念頭に入れており、これまでの観光振興や地方移住促進策といった地方創生推進交付金の枠組みでは、現状に対応しにくいと考えています。そのため、より稼げる地方を目指し、交付上限を設けないなどの変更(※1)をしており、対象企業がより柔軟に補助金を活用できるようにしています。
※1 交付上限額は以下のように一応設定されていますが、所得向上等の観点から高い効果が見込まれる事業は、交付上限額を超えて交付することが可能です。
【都道府県】
先駆事業 6.0億円(28年度:4.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.5億円(28年度:1.0億円)
【市区町村】
先駆事業 4.0億円(28年度:2.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.0億円(28年度:0.5億円)
これにより事業会社は地方創生推進交付金を活用し、地方行政を巻き込んだ「稼げる事業」を推進しやすくなったことで、ビジネスチャンスが広がりました。
地方で事業を行いたい方は是非御検討ください!
政府は、人工知能(AI)やロボット、医療・介護サービスなどの最先端技術を念頭に入れており、これまでの観光振興や地方移住促進策といった地方創生推進交付金の枠組みでは、現状に対応しにくいと考えています。そのため、より稼げる地方を目指し、交付上限を設けないなどの変更(※1)をしており、対象企業がより柔軟に補助金を活用できるようにしています。
※1 交付上限額は以下のように一応設定されていますが、所得向上等の観点から高い効果が見込まれる事業は、交付上限額を超えて交付することが可能です。
【都道府県】
先駆事業 6.0億円(28年度:4.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.5億円(28年度:1.0億円)
【市区町村】
先駆事業 4.0億円(28年度:2.0億円)
横展開・隘路打開事業 1.0億円(28年度:0.5億円)
これにより事業会社は地方創生推進交付金を活用し、地方行政を巻き込んだ「稼げる事業」を推進しやすくなったことで、ビジネスチャンスが広がりました。
地方で事業を行いたい方は是非御検討ください!


 3.受給額
(1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
①大企業
対象若年労働者:1/4
対象新規学卒者:-
②中小企業
対象若年労働者:1/3
対象新規学卒者:1/3
(2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。
3.受給額
(1)支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
①大企業
対象若年労働者:1/4
対象新規学卒者:-
②中小企業
対象若年労働者:1/3
対象新規学卒者:1/3
(2)ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限とします。


 2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは?
ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。
①求人における活用(1)
ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。
②求人における活用(2)
雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
③在職労働者の職業能力の評価における活用
ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用
在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
⑤求職活動支援書の作成における活用
在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。
2.企業にとってのジョブ・カードのメリットは?
ジョブ・カードは、個人のキャリアの把握、能力の向上に効果を発揮しますが、もちろん企業にも次のようなメリットがあります。
①求人における活用(1)
ジョブ・カードを履歴書の追加資料などとして活用することにより、履歴書だけでは分かりにくい応募者の職業能力に関する情報を、決められた様式によって得ることができます。なお、応募書類として活用されるジョブ・カードの情報は労働者本人の意思により提出されるものです。本人の意思に反して提出を求めることはできません。
②求人における活用(2)
雇用型訓練においてジョブ・カードを活用することにより、訓練成果を業界共通の「ものさし」によって訓練の評価をすることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
③在職労働者の職業能力の評価における活用
ジョブ・カードを活用して在職労働者の実務成果、職業能力を評価することにより、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進を図ることができます。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
④在職労働者へのキャリアコンサルティング等での活用
在職労働者の職業能力開発の促進のため、事業主によるキャリアコンサルティング、職業訓練等を行う場合、ジョブ・カードを活用することにより、訓練の必要性が明確になるなど、これらの取組みが一層効果的なものとなります。また、一定の要件を満たす場合には、国からの助成金を受けられます。
⑤求職活動支援書の作成における活用
在職労働者(45歳以上の65歳未満)が離職することとなり、事業主が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」(任意様式)の作成を行う場合に、ジョブ・カードの情報を活用することができます。また、45歳未満の離職予定の方に対しても同様の書面を交付することにより、円滑な求職活動を支援することができます。
 3.ジョブ・カードが必要な助成金とは?
ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。
①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)
パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。
訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。
②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度)
「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。
人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。
ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか?
また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください!
3.ジョブ・カードが必要な助成金とは?
ジョブ・カード作成が必須となる代表的な助成金として、以下のものがあります。
①キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)
パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を訓練させ、正社員として登用するのに発生する費用を最大50万円助成します。
訓練受講者はジョブ・カードを前もって作成し、事業主が作成した訓練カリキュラム、訓練計画予定表に基づき、ジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます。そして、訓練の必要性の有無について確認を受けます。
②人材開発支援助成金(セルフ・キャリアドック制度)
「セルフ・キャリアドック制度」とは、従業員のキャリア形成支援のために、就業年数や役職就任などの節目にて、従業員がキャリアコンサルティングを受ける機会を、企業が設ける仕組みのことです。
人材開発支援助成金の「キャリア形成支援制度導入コース」では、このセルフ・キャリアドック制度の導入を必須としており、これを実施した場合、最大60 万円の助成金を受けられます。ジョブ・カードをもとにキャリアコンサルティングを受けるので、あらかじめジョブ・カードを作成しておく必要があります。
ジョブ・カードを作成すれば、従業員のキャリアアップに役立つだけでなく、助成金も受給できます!一度ジョブ・カードを作成してみてはいかがでしょうか?
また、助成金なうではキャリアアップ助成金の他にも、人材育成系の助成金を多数そろえております。是非ご利用ください!

 5.補助率及び補助限度額等
対象経費の2分の1の額又は20万円のうち、いずれか少ない額
※千円未満は切捨て、同一団体への補助金は2年間を限度とします。
6.対象経費
謝金、交通費(宿泊、食費は除く)、会場借上料及び設備使用料、消耗品購入費、展示会及び見本市等の出展費・参加費、印刷製本費、ホームページ開設等の広告宣伝費、調査委託費
7.申請方法
○申請期間
平成29年4月17日(月)午前9時から 平成29年12月28日(木)午後5時まで
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
○申請書の提出方法
1.事前相談
問合せ先に電話又は電子メールで連絡し、日程調整を行ってください。
2.申請受付
申請書類を全て揃え、持参してください。先着順に受付けます。
8.報告方法
○提出期限
平成30年2月28日まで
○提出方法
1.提出書類
実績報告書(第12 号様式)、収支決算書(第13 号様式)
第13 号様式に記載された経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書等)
その他市長が必要と認める書類
2.提出方法
報告書類を全て揃え、持参してください。
書類不備の場合は、補助金を交付しません。
9.問合せ先
横浜市経済局ものづくり支援課 「チームdeものづくり」担当
(電 話)045-671-3489 (メール) ke-group@city.yokohama.jp
〒231-0016 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
もし複数の企業でないと対応できない事業に取り組みたくなったら、このような補助金が地元の自治体にないか探してみてはいかがでしょうか?
5.補助率及び補助限度額等
対象経費の2分の1の額又は20万円のうち、いずれか少ない額
※千円未満は切捨て、同一団体への補助金は2年間を限度とします。
6.対象経費
謝金、交通費(宿泊、食費は除く)、会場借上料及び設備使用料、消耗品購入費、展示会及び見本市等の出展費・参加費、印刷製本費、ホームページ開設等の広告宣伝費、調査委託費
7.申請方法
○申請期間
平成29年4月17日(月)午前9時から 平成29年12月28日(木)午後5時まで
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
○申請書の提出方法
1.事前相談
問合せ先に電話又は電子メールで連絡し、日程調整を行ってください。
2.申請受付
申請書類を全て揃え、持参してください。先着順に受付けます。
8.報告方法
○提出期限
平成30年2月28日まで
○提出方法
1.提出書類
実績報告書(第12 号様式)、収支決算書(第13 号様式)
第13 号様式に記載された経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書等)
その他市長が必要と認める書類
2.提出方法
報告書類を全て揃え、持参してください。
書類不備の場合は、補助金を交付しません。
9.問合せ先
横浜市経済局ものづくり支援課 「チームdeものづくり」担当
(電 話)045-671-3489 (メール) ke-group@city.yokohama.jp
〒231-0016 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル5階
もし複数の企業でないと対応できない事業に取り組みたくなったら、このような補助金が地元の自治体にないか探してみてはいかがでしょうか?


 3.審査基準
助成金の審査基準は、
①プロジェクトの新規性
②プロジェクトの市場性
③プロジェクトの実現可能性
④経済・社会への貢献内容
などとなります。
株式保有の審査基準は、
①企業内容
②助成金交付時・債務保証時のプロジェクトの進展状況
③事業計画の妥当性
④資金使途
などとなります。
4.募集期間
平成29年度の第2回目は、9月1日(金)~10月31日(火)(最終日10月31日の当日消印のあるものまで有効です)が募集期間となります。
3.審査基準
助成金の審査基準は、
①プロジェクトの新規性
②プロジェクトの市場性
③プロジェクトの実現可能性
④経済・社会への貢献内容
などとなります。
株式保有の審査基準は、
①企業内容
②助成金交付時・債務保証時のプロジェクトの進展状況
③事業計画の妥当性
④資金使途
などとなります。
4.募集期間
平成29年度の第2回目は、9月1日(金)~10月31日(火)(最終日10月31日の当日消印のあるものまで有効です)が募集期間となります。


 5.補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、本事業の目的に沿って策定された事業計画に基づき実施する取組に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 機械施設整備費
機械、簡易な施設等の購入、借用及び改良に要する経費
イ 原材料、消耗品費
新商品の開発に必要な原材料、副材料及び消耗品の購入に要する経費
ウ 新商品開発費
新商品の試作、既存商品の改良等の外部業者への委託、開発・改良に向けたスキルアップに要する経費
エ 販売促進費
フェア等への参加、流通販売調査等販売促進に要する経費
オ アドバイザー派遣費
専門アドバイザー等からの助言・指導に要する謝金及び旅費
カ 事務費
事務用品の購入に要する経費
キ その他の経費
上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費
6.採択要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 農林水産資源を活用する取組であること。
イ 家族経営協定で起業部門を設定しているか、または、事業実施期間中に起業部門を設定した協定の締結が確実であること。
ウ 事業内容の実現性が高い取組であること。
エ 地域における雇用創出や関連産業との連携など、地域全体への波及効果が高い取組であること。
7.その他留意事項
他の知的財産権を侵害しないこと。
5.補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、本事業の目的に沿って策定された事業計画に基づき実施する取組に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
ア 機械施設整備費
機械、簡易な施設等の購入、借用及び改良に要する経費
イ 原材料、消耗品費
新商品の開発に必要な原材料、副材料及び消耗品の購入に要する経費
ウ 新商品開発費
新商品の試作、既存商品の改良等の外部業者への委託、開発・改良に向けたスキルアップに要する経費
エ 販売促進費
フェア等への参加、流通販売調査等販売促進に要する経費
オ アドバイザー派遣費
専門アドバイザー等からの助言・指導に要する謝金及び旅費
カ 事務費
事務用品の購入に要する経費
キ その他の経費
上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費
6.採択要件
次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 農林水産資源を活用する取組であること。
イ 家族経営協定で起業部門を設定しているか、または、事業実施期間中に起業部門を設定した協定の締結が確実であること。
ウ 事業内容の実現性が高い取組であること。
エ 地域における雇用創出や関連産業との連携など、地域全体への波及効果が高い取組であること。
7.その他留意事項
他の知的財産権を侵害しないこと。
 8.募集期間
平成29年7月20日(木 )~8月31日(金)
9.応募方法等
必要書類を作成し、最寄りの地域県民局地域農林水産部農業普及振興室へ提出するとともに、別途開催する審査会議において、プレゼンテーションをしていただきます。
10.お問合せ先
農林水産政策課農業改良普及グループ
電話:017-734-9473 FAX:017-734-8133
8.募集期間
平成29年7月20日(木 )~8月31日(金)
9.応募方法等
必要書類を作成し、最寄りの地域県民局地域農林水産部農業普及振興室へ提出するとともに、別途開催する審査会議において、プレゼンテーションをしていただきます。
10.お問合せ先
農林水産政策課農業改良普及グループ
電話:017-734-9473 FAX:017-734-8133

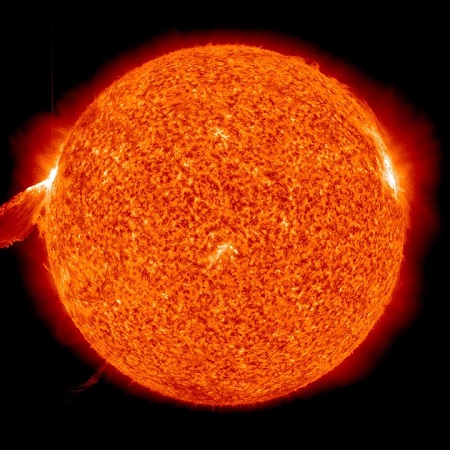
 3.助成対象機器等
区内の事業所等に、以下の対象機器等を導入する中小企業等が対象となります。
同一種類の助成については、一つの建物に対して1回限りとなります(年度が替わっても一度助成を受けた種類の助成に対しては対象となりません)。
1.太陽光発電システム
2.太陽熱温水器
3.太陽熱ソーラーシステム
4.高効率・LED照明機器(※新規設置は対象外)
5.遮熱塗装等断熱改修(※新築は対象外)
6.空調設備機器(※新規設置は対象外)
7.省エネ型小規模燃焼機器等(小型ボイラー、ガス発電給湯器、燃料電池)への改修(※新規設置は対象外)
8.電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車(※平成25年4月1日以降に購入したもの)
9. 蓄電池
4.問合せ先
環境課環境計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8228 ファクス:03-5698-1538
3.助成対象機器等
区内の事業所等に、以下の対象機器等を導入する中小企業等が対象となります。
同一種類の助成については、一つの建物に対して1回限りとなります(年度が替わっても一度助成を受けた種類の助成に対しては対象となりません)。
1.太陽光発電システム
2.太陽熱温水器
3.太陽熱ソーラーシステム
4.高効率・LED照明機器(※新規設置は対象外)
5.遮熱塗装等断熱改修(※新築は対象外)
6.空調設備機器(※新規設置は対象外)
7.省エネ型小規模燃焼機器等(小型ボイラー、ガス発電給湯器、燃料電池)への改修(※新規設置は対象外)
8.電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車(※平成25年4月1日以降に購入したもの)
9. 蓄電池
4.問合せ先
環境課環境計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8228 ファクス:03-5698-1538







 4.助成対象外経費
公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
5.申請できる期間
申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請期間:
①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内
②毎年4月1日から定数に達するまで
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ・申請先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
アクセスマップ
電話3870-8400(直通)
4.助成対象外経費
公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関から専門家の派遣を受けた場合の経費
5.申請できる期間
申請は先着順で受付け、年間予算額に達した時点で、助成金の交付は終了します。
申請期間:
①公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内
②毎年4月1日から定数に達するまで
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付
6.問い合わせ・申請先
中小企業支援課創業支援係
〒120-0034
足立区千住一丁目5番7号あだち産業センター2階
アクセスマップ
電話3870-8400(直通)



 3.助成額
助成額としては、「しらべる助成」が上限 100万円、「そだてる助成」が上限なし(過去3年間の実績平均519万円/2年)となっています。
運営の中心となる組織の法人格の有無・種類は問わないので、だれでも応募できるという非常に間口の広い助成事業となっています。
3.助成額
助成額としては、「しらべる助成」が上限 100万円、「そだてる助成」が上限なし(過去3年間の実績平均519万円/2年)となっています。
運営の中心となる組織の法人格の有無・種類は問わないので、だれでも応募できるという非常に間口の広い助成事業となっています。


 3.支援内容・支援規模
〔補助対象経費〕
補助事業の実施により、小口投資の募集開始に至った場合にその時点までに必要となる次の経費
①指定事業者が実施する出資対象事業としての適正性に関する評価調査(事業適正評価調査)に要する経費
②匿名組合契約により小口投資を募集するために必要となる小口投資取扱ホームページの開設及び契約システム等の利用に要する経費
〔補助上限額〕
1,000千円(1事業者当たり)
4.募集期間
平成29年度:平成29年6月1日から平成29年8月31日
5.対象期間
交付決定日から平成30年2月28日まで
6.問合せ先
奈良県 産業・雇用振興部 産業政策課 産業政策推進係
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
TEL:0742-27-8814
FAX:0742-27-4473
お金が足りなくてもクラウドファンディングで資金を募れば大丈夫!・・・と言いたいところですが、出資者とのお金のやり取りや事業の実現可能性など、最低限のことはきちんとしておくことが肝要です。
3.支援内容・支援規模
〔補助対象経費〕
補助事業の実施により、小口投資の募集開始に至った場合にその時点までに必要となる次の経費
①指定事業者が実施する出資対象事業としての適正性に関する評価調査(事業適正評価調査)に要する経費
②匿名組合契約により小口投資を募集するために必要となる小口投資取扱ホームページの開設及び契約システム等の利用に要する経費
〔補助上限額〕
1,000千円(1事業者当たり)
4.募集期間
平成29年度:平成29年6月1日から平成29年8月31日
5.対象期間
交付決定日から平成30年2月28日まで
6.問合せ先
奈良県 産業・雇用振興部 産業政策課 産業政策推進係
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
TEL:0742-27-8814
FAX:0742-27-4473
お金が足りなくてもクラウドファンディングで資金を募れば大丈夫!・・・と言いたいところですが、出資者とのお金のやり取りや事業の実現可能性など、最低限のことはきちんとしておくことが肝要です。


 4.補助対象
ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
イ、構築物、機械装置に係る固定資産税
※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3%
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上
5.補助率
※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額
①移転型
4/4(1年目)
3/4(2年目)
2/4(3年目)
②拡充型
3/3(1年目)
2/3(2年目)
1/3(3年目)
6.お問合せ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4744
FAX:055-933-1412
E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp
4.補助対象
ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
イ、構築物、機械装置に係る固定資産税
※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3%
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上
5.補助率
※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額
①移転型
4/4(1年目)
3/4(2年目)
2/4(3年目)
②拡充型
3/3(1年目)
2/3(2年目)
1/3(3年目)
6.お問合せ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4744
FAX:055-933-1412
E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp
























