はじめに:業種分類は「企業データの地図」
マーケティングや営業戦略、データ整備を進めるうえで、「業種分類」は欠かせない軸のひとつです。
たとえば、業種ごとのターゲティングや、市場分析、競合調査、顧客データベースの整備など、業種分類をベースに行われる業務は多岐にわたります。
ところが、日本には複数の業種分類体系が存在し、それぞれに特徴や用途が異なります。
本記事では、主に流通している以下の3つの分類体系について、違いや判定基準を解説し、実務でどのように活用すべきかをご紹介します。
業種とは何か?業態との違いと分類の考え方
まず前提として、「業種」とは何を指すのでしょうか。
- 業種とは、企業や事業所が行っている事業内容の種類を指します。(例:建設業、小売業、情報通信業など)
- 業態とは、その業種内での営業形態やビジネスモデルを指します。(例:飲食業の中でも「ファストフード店」「高級レストラン」など)
「業種」は、主に外部から企業を把握するための分類軸であり、統計やマーケティング、行政手続きにおいて使用されます。
業種はどうやって決まるのか?──判定の基準
業種分類は「企業の何を見て」決まるのでしょうか?
実は分類体系ごとに、以下のような判断基準が設けられています。
| 分類体系 | 判定基準 |
|---|---|
| 日本標準産業分類(JSIC) | 主たる事業の内容(部門別の売上高を基準に) |
| 経済センサス分類 | 事業所の実態に基づく申告内容(調査票への記載) |
| 民間独自分類(例:法人電話帳データ) | 申請時の自己申告(企業が申告した業種) |
よくあることですが、1つの企業が複数の事業を行っている場合、一般的には「もっとも主要な事業」に基づいて分類がなされます。
しかし実務上は「業種が曖昧・またがる」「時間とともに変化する」といった課題もあり、データ整備には工夫が求められます。
業種分類の3つの体系と特徴
それでは、実際に流通している代表的な3分類について、それぞれの特徴と使われ方を見ていきましょう。
1. 日本標準産業分類(JSIC)|総務省
日本標準産業分類は、総務省が公的に定めた統一的な業種コード体系です。
統計調査や行政手続きでの使用を前提としており、日本国内では最も標準的かつ制度的に整備された分類です。
特徴
- 階層構造:大分類(20区分)、中分類、小分類、細分類の4段階
- 判定基準:事業所の主要な経済活動(直近1年の売上が最も高い事業、部門)に基づく
- 用途:国勢調査、雇用保険・労災、公共調達、行政の許認可など
具体例(抜粋)
- G 情報通信業
└ 39 インターネット附随サービス業
└ 3911 ポータルサイト・サーバ運営業
留意点
- 表現が制度的・抽象的であるため、マーケティング実務では使いにくい面も
2. 経済センサスにおける業種分類|総務省・経産省
「経済センサス」は、日本国内の全ての事業所を対象にした統計調査で、
その際に用いられる業種分類は、日本標準産業分類をベースにしつつ、一部業種は追加・削除されており、調査票への記載内容や実態に即して運用されるのが特徴です。
特徴
- 実地調査や事業者の回答内容により、現場に即した判定がなされる
- 複数事業を行う事業所は、最も代表的なものに基づいて分類される
例
- 小売業だがネット販売が主であれば「電子商取引小売業」と分類される可能性
留意点
- 回答者の記載方法により、分類の正確さがばらつくことがある
3. 民間調査会社・データベンダーによる独自業種分類
多くの民間調査会社やデータベンダーでは、独自の業種分類体系を用いています。
これは、調査・データ提供・マーケティング支援の実務で柔軟に使えるように整備されたものです。
【当社事例】法人電話帳データの業種分類
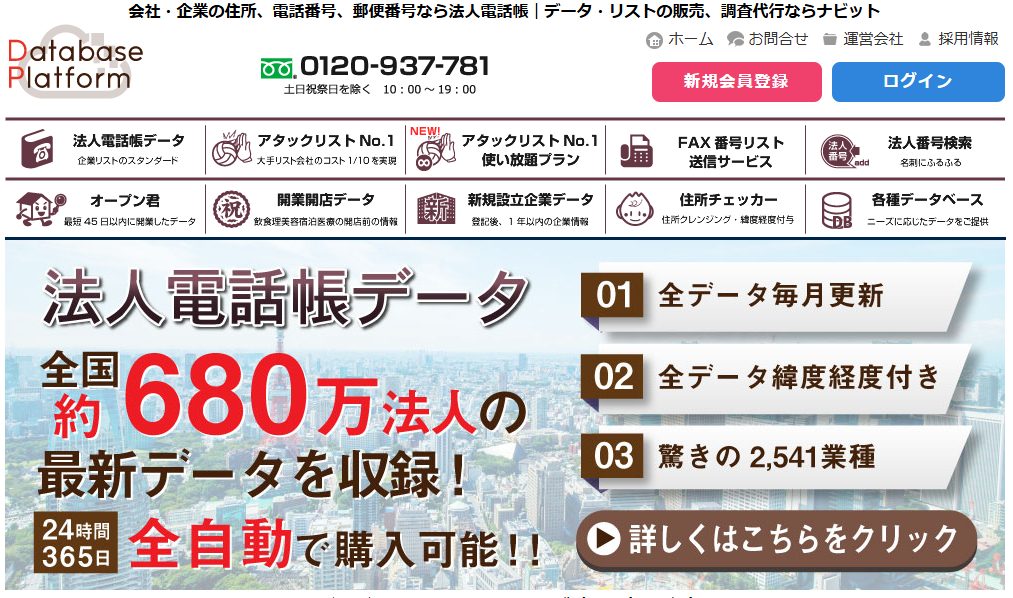
たとえば当社では、長年にわたり「法人電話帳データ」を整備・提供しており、
企業が電話帳掲載の申請を行う際に自己申告した業種に基づいて、大分類・中分類(198業種)・小分類(2,541業種)の3階層で分類しています。
このため、下記のような特長があるものです。
- 申告ベースのため、現場に即した業種が把握でき、信頼性も高い
- 業種名が直感的で、営業現場でも使いやすい
- 例えば「飲食店」>「日本料理」の中に「うなぎ料理店」「お好み焼き店」「しゃぶしゃぶ料理店」などの粒度で整理
当社分類の強み
- 実務ベースでの柔軟な粒度
- JSIC・経済センサス分類への変換にも対応(文字列近似によるマッピング)
当社分類の活用事例
- 「学童保育所」にピンポイントでアプローチ!(C社様・教育系ICT業)
- 他の業種分類には「小学校」または「公立/私立小学校」の分類はあっても「学童保育所」の分類がない
- 「キジ畜産業」にピンポイントでアプローチ!(D社様・牧草卸売業)
- 当社の場合、たとえば畜産業関連は次のような粒度で電話番号データを管理しています。ニッチなビジネス用途にもスムーズにお使いいただけます!
- 養鶏業
- 養蚕農業
- ウサギ畜産業
- 養豚業
- 養蜂業・養蜂場
- キジ畜産業
- 養鶉業・養鶉場
- 当社の場合、たとえば畜産業関連は次のような粒度で電話番号データを管理しています。ニッチなビジネス用途にもスムーズにお使いいただけます!
なぜ業種分類が複数あるのか?どれを使うべきか?
分類体系が複数ある理由は、それぞれの目的が異なるためです。ご利用の目的にあった業種が何にあたり、どのような定義づけがされているものかを事前に確認することをおすすめします。
| 分類体系 | 主な目的・用途 |
|---|---|
| 日本標準産業分類 | 行政・統計(制度的信頼性) |
| 経済センサス分類 | 国勢レベルでの実態把握 |
| 独自業種分類(民間) | 営業、マーケ、データ提供(実務適合性) |
実務での課題
- 自社データが公的分類と整合しない
- 1企業が複数の業種にまたがる
- 類似業種がバラバラに登録されている
これらを解決するためには、業種マッピング(変換)や分類体系の選定ルールが不可欠です。
当社のデータ整備サービスができること
そこで当社では、以下のような支援もご提供しています。
- 「法人電話帳データ」による信頼性の高い業種分類付きリストの提供
- 各企業に対し、「日本標準産業分類」「経済センサス分類」など他分類体系への変換も対応
まとめ:業種分類を味方に、ビジネスをもっとスムーズに
業種分類は、企業データを活用する上での“ナビゲーションシステム”です。
分類体系の違いを理解し、自社の目的に応じた業種の使い方をすることで、
より精度の高いマーケティングや営業活動が実現できます。
お問い合わせ・資料請求はこちら
- 自社の顧客データに業種コードを付けたい
- 統一的な業種分類で営業リストを整備したい
- 日本標準産業分類とのマッピングを自動化したい
そんな課題をお持ちの企業様は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。








