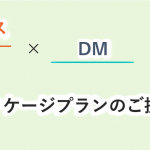はじめに:「うちには関係ない」では済まされない! 下請法とは
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」という言葉を耳にしたことはあっても、
「うちは中小企業だから関係ない」と思っている方も少なくありません。
しかし実際には、中小企業同士の取引でも適用されるケースがあり、
知らずに契約書の不備や支払遅延などの違反行為に該当してしまうリスクも存在します。
この記事では、企業間取引に携わる方に向けて、下請法の基本知識・適用範囲・典型的な違反例・実務チェックポイントをわかりやすく解説します。
※本ブログに記載の情報は、2025年5月20日現在のものです。
法律の改正、施行は日々行われますので、常に最新の情報を参照してください。
1. 下請法の正式名称とその背景
下請法の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。
これは、独占禁止法の特別法として1956年に制定された法律で、
「親事業者がその優越的地位を濫用して、下請事業者に不利益を与えることを防止する」ことを目的としています。
詳しくは:中小企業庁「下請代金支払遅延等防止法」
監督・指導は、公正取引委員会および中小企業庁が共同で行っています。
2. 適用対象は? うちには関係ありますか?
下請法は、「親事業者」が「下請事業者」に対して、製造委託・修理委託・情報成果物作成・役務提供などを行う特定の取引に適用されます。
「親」「下請」の関係は、次の2点で判断されます:
- 資本金規模の差
親事業者の方が大きい - 取引内容
下請事業者に業務を委託(例:製品の製造、ソフト開発、デザイン作成など)
例:中小企業でも「親事業者」になることがある
たとえば、自社の資本金が1億円未満であっても、資本金1,000万円の企業に対して業務を委託すれば「親事業者」となり、下請法の規制対象になります。
つまり、「資本金が大きい=親」「中小だから関係ない」という考え方はNGです。
補足:官公庁・外郭団体との取引はどうなる?
- 資本金が適用の要件に入るため、国や地方自治体(官公庁)が発注する契約は、原則として下請法の適用対象外です。
- ただし、外郭団体・第3セクター・独立行政法人等が委託元となる場合は、
その法人格(例:株式会社、社団法人等)や資本金額、取引内容に応じて、下請法の適用対象となることがあります。
実際の適用可否はケースバイケースとなるため、発注元の組織形態と契約内容の確認が必要です。
3. 違反行為の例(義務4項目、禁止行為11項目)
公正取引委員会では、下請法違反につながる行為として以下の義務4項目、禁止行為11項目を挙げています。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ①発注書面を交付する義務 | 発注書面の交付を行う |
| ②取引に関する書類を作成・保存する義務 | 取引完了にあたり書類を2年間保存する |
| ③支払期日を定める義務 | 支払期日を納品から起算し60日以内に定める |
| ④遅延利息を支払う義務 | 納品から起算し60日以内に下請代金が支払われない場合、遅延利息(年利14.6%)を支払う |
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ①受領拒否 | 発注した物品等の受領を拒否する |
| ②下請代金の支払い遅延 | 発注した物品等の代金を、受領から60日以内に支払わない |
| ③下請代金の減額 | 下請事業者に責任がないのに、下請代金を発注後に減額する |
| ④返品 | 下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品する |
| ⑤買いたたき | 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金を不当に定める |
| ⑥物の購入強制・役務の利用強制 | 正当な理由なく親事業者が指定する物品、役務を強制的に購入させる |
| ⑦報復措置 | 違反行為を通報したことを理由に、下請事業者に不利益な扱いをする |
| ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償支給する原材料費を、下請代金の支払い日より早く払わせる |
| ⑨割引困難な手形の交付 | 一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形で支払いを行う |
| ⑩不当な経済上の利益の提供要請 | 協賛金や従業員の派遣など自己の利益となることをむやみに要請する |
| ⑪不当な給付内容の変更・やり直し | 発注内容の変更、追加作業を行わせる際、その費用を負担しない |
これらの違反があると、勧告・企業名の公表・指導・立入検査の対象になることがあります。
4. 実務で気をつけるべきポイント
4-1 親事業者としての3つのチェックポイント
①契約書は必ず交わす(口頭はNG)
- 発注内容・納期・金額・成果物の範囲などを明記
- 書面または電磁的記録(PDFやメール等)で残すことが重要
②支払・受領記録は必ず保管
- 納品書、請求書、支払明細、振込記録を3年間以上保存
- 監査・立入調査時の対応に備える
③単価の引き下げ・値引き依頼には慎重に
- 値引き交渉は合意が前提
- 強要や一方的な減額は優越的地位の濫用と判断される可能性あり
4-2 下請け業者として、自社が「いじめられている」と感じたら
下請法は、親事業者が注意すべき法令であると同時に、
下請事業者が不当な扱いを受けていると感じた場合にも、守ってくれる法律です。
たとえば、以下のような経験がある場合は注意が必要です。
- 契約書も発注書もなく、口頭だけで業務を依頼された
- 納品したのに「内容が悪い」として支払が遅れている
- 原材料費や運賃が上がっても、値上げ交渉を拒否されている
- 技術仕様書や成果物が、別の取引先に無断で再利用された
- 苦情や改善要望を伝えた途端に、発注が止まった
これらは、下請法で定められている「親事業者の禁止行為」に該当する可能性があります。
どう対応すればいい?
- 証拠を残すことが第一です。
メール・チャット・見積書・納品書・請求書などを必ず保存しましょう。 - 相談窓口に頼るのも有効です。
中小企業庁や公正取引委員会では、匿名での相談・申告も受け付けています。
「相手が大手だから」「長年の取引だから」と我慢しすぎず、
正当な取引環境を求めることは企業の持続可能性を守る行動でもあります。
5. チェックリスト:うちは大丈夫?
以下に該当する場合、下請法に違反している可能性があります。
☐ 親事業者として契約書を発行していない
☐ 発注内容をメールだけで伝えている
☐ 成果物に対して支払を渋ったことがある
☐ 一方的に発注をキャンセルしたことがある
☐ 業務委託の際、相手の資本金や関係性を確認していない
1つでも該当する場合は、社内ルールやフローの見直しをおすすめします。
6. 当社の取引整備サポートとの関連
当社では、「法人電話帳データ」や業種分類・企業間関係データの整備を通じて、
企業同士の取引関係や親子関係の明確化を支援しています。
下請法対応においても、以下のような形でご活用いただいています。
- 業種分類に基づく「取引適用範囲」の把握
- 類似企業の分類比較による業務委託の適正性チェック
- 親子企業関係の整理(※社内ガバナンス強化にも有効)
法務・経営企画・営業部門の方に広くご活用いただいております。
7. まとめ:下請法対応は信頼される企業の基盤に
下請法は、企業間取引の信頼性を守るための大切な法律です。
中小企業であっても、親事業者になるケースは十分にあります。
「知らなかった」では済まされない時代、いま一度、自社の契約・取引慣行を見直してみてはいかがでしょうか。
関連リンク・お問い合わせ
公正取引委員会「下請法の概要」
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
公正取引委員会「違反事例集(最新)」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shitaukejiken/index.html
法令原文(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000120