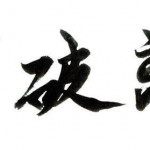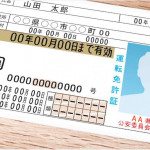こんにちは!!「炎のタックラー マイク75」です!!
月日が経つのは早いもので、7月もあっという間に終わってしまいそうですね。
暑さの厳しい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
本日は「初対面の人に信用される人とそうでない人の違いは、どこにあるのか?」に
迫ってみたいと思います。

よく営業は信用されてなんぼと言われていますが、お客様からするとどの営業から
買うのかは非常に重要な要素になっていたりします。
選ぶ側も人間、気に入らない営業からは買いたくないものです。
では、どうしたら初対面の人に好感を持たれて、信用を勝ち得るのか?
それは会話の中に盛り込まれている、“ある要素”にありました。
初対面の人に信用される人が 会話に盛り込んでいる3つの要素初対面でも相手から
信用を得やすい人は大抵、ある要素を話に盛り込んでいます。
人が話す内容の信憑(しんぴょう)性については数多くの研究報告がありますが、
今回はバーローら(1966)が見い出した信憑性を構成する3つの要素を紹介します。
・要素1 信頼性(安全性)
→相手が信頼できるに値するか、信頼しても大丈夫かの度合い
・要素2 専門性(資格性)
→その内容を話すに値する人か、特定の分野でどれだけ深く関わっているかどうかの
度合い
・要素3 力動性
→話し手がエネルギッシュかどうかのエネルギッシュさの度合い
初対面でも相手の信用を得やすい人が話に盛り込んでいる要素、その一つ目は、
「信頼性」を高めることです。
ここでいう信頼性は、話し手の真面目さ、誠実な人柄、相手を説き伏せようとしてこない、
説得の結果に対して利益を持たないことに由来します(Wheelessら ,1977 & McGinnies, 1980)。
また、別の研究では、自分の利益に反することを述べたときの方が相手からの信頼性は
高くなるともいわれています(Walster,1962)。
初対面での会話では、自分の利益を取りにいくような話から入ったり、相手を説き伏せ
ようとする姿勢を見せたりするのは避けましょう。
反面教師となるのが、顧客のニーズを聞かず、売り込みたい商品の説明に終始する
営業活動です。
聞き手の事情を無視したコミュニケーションは、信用を毀損します。
2つ目は、自分の「専門性」をアピールすることです(Horaiら, 1974)。
専門性とは、話し手の学歴や経歴、資格や専門分野、特殊な経験などです。
専門性をしっかりアピールするためにも、自身の専門性にかかわる情報はあらかじめ
書き出しておき、適宜、自分の話に盛り込むようにします。
士業の人たちが最初から信用されやすいのは、少なくともその分野における国家資格を
得ているという分かりやすい専門性が伝わるからです。
専門性のアピールによって、こちらの能力を相手に示すことができます。
3つ目は、力動性を感じさせる話し方をする。つまり、エネルギッシュに話すことです。
後述しますが、エネルギッシュであること(力動性)は、その人の信憑性を高めることに
つながります。
自己紹介では力強く、堂々と話すことで相手から信用されやすくなるのです。
聞き手がこの3つを満たしていると感じたとき、初対面であっても話し手への信用は
一気に高まります。
3つの要素を意識して話し方を演出していきましょう。
初対面の相手に信用してほしいなら、 自分の話し方をスマホで録画してみましょう。
ここからは、3つ目の要素「力動性」を高めるコツに絞って解説します。
なぜなら、力動性、エネルギッシュに話すことは最も簡単に取り組むことのできる要素
だからです。
しかも、相手があなたに力動性を感じると、連動して信頼性、専門性の評価も高まります。
これだけエネルギッシュなのだから、人柄も良いに違いない。専門性もあって、これだけ
エネルギッシュなら、成果を出してくれるはず。
力動性が与えるインパクトが、そんな連想をさせるからです。
力動性を感じさせる話し方のポイントは、胸を張って元気よく話すこと。
プロ野球の大谷翔平選手やタレントの芦田愛菜さんなどをイメージしてください。
シンプルすぎる取り組みかもしれませんが、私たちは自分の話し方について客観視する
機会がほとんどありません。
無自覚にうつむき加減でボソボソと話していたり、小声で早口になっていたり、事務的で
つっけんどんな口調になっていたり……こうした話し方が、相手に信用してもらえない
原因になっている可能性があります。
ですから、力動性を磨くには、まず自分がどのような話し方をしているのかを知ることが
大切です。
スマートフォンやPCの内蔵カメラで自撮りし、自分がどのような話し方をしているのか
確認しましょう。
すると「えー」とか「あー」とかの口癖、猫背で頼りない姿勢、目が泳いでいる、声の
小ささなど、自分の悪いクセが分かるはずです。
一つずつでよいので直していくよう心がけましょう。

相手の信用を損なわないためのコツと“相手を信頼しすぎない”ための防衛法
最後に提案や交渉ごとにおいて信用を損なわないようにするためのコツと相手が信用の
3要素を盛り込んで話をしてきたときの防衛法をお伝えします。
信用を損なわないために注意したいのは、自分の発言に論理矛盾が生じないようにする
ことです。
要素1「信頼性(安全性)」や要素2「専門性(資格性)」が揺らぐと、いかに力動性が
あっても聞き手は交渉や会話の内容にうさんくささを感じてしまいます。
例えば商談時に「より良いものをつくるためには、原価がいくらかかろうが、弊社は
赤字になっても構いません」と力強く言っておきながら、条件交渉の段階になって
「このフィーでは、原価割れしてしまいます」と伝えたら、どうでしょう?
相手は「あれ? さっきと言っていたことが違うじゃない」と思い、あなたの信頼性
(安全性)が揺らぎます。
交渉を優位に運ぶためにも、自分の利益に反する条件を伝えるときは、風呂敷を広げすぎ
ないようにしましょう。
「より良いものをつくるためには、原価がいくらかかろうが、弊社は赤字にさえなら
なければ問題ありません」といった具合です。
なお、3つの要素を満たした相手と話すと、ついつい相手を過大評価してしまい、途中で
「なんか、思っていたのと違うかも……」と物事がうまくいかなくなるケースも出てきます。
これは仕事だけでなく、プライベートでもよく起こることです。
こうした事態を防ぎ、身を守るためには、相手の“話し方”と“話している内容”を
切り離すことが重要です。
一例を挙げると、私は相手の話す姿を見ているようで、話の内容だけにしか注目しない
ようにしています。
また、相手から見られないような状況(PCの画面越しでカメラがOFFなど)なら、目を
閉じて相手の話を聞きます。外見や体の動きと話の内容を切り離して受け取るためです。
他にも重要な商談で、相手の声色や話しているスピードが会話内容の信憑性に影響が
ありそうなら、相手の話を録音し、文字起こし(※)をします。
メモも有効ですが、その場合は自分の主観的な感想は挟まず、相手の口にした事実を
箇条書きにまとめるように心がけましょう。
文字だけで見てみると、実は大した話はしていないとか、よくよく読むと論理矛盾が
多いとかといったことに気付けるようになります。
相手を「信用する、しない」「信用される、されない」は、非常に繊細で感覚的な判断に
なってきます。
いいことを話しているのに、相手に信用・信頼してもらえないのはとてももったいない
ことです。
客観的な事実(実績や能力)を、より魅力的に見せる話し方に意識を向けてみましょう。
それだけで、聞き手から見た印象はポジティブなものに変わるのではないでしょうか。