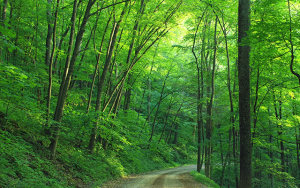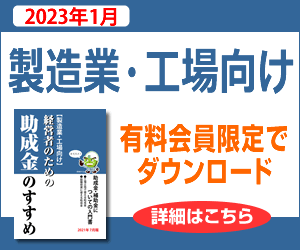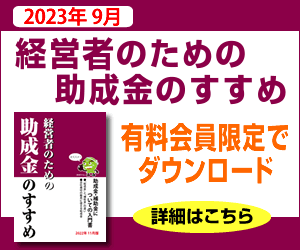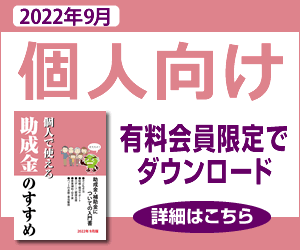ビジネスにおいて耳にするGビズID(GBIZ ID)。
「聞いたことはあるけれど詳しく分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回はGビズID(GBIZ ID)について解説します!
ビジネスにおいて耳にするGビズID(GBIZ ID)。
「聞いたことはあるけれど詳しく分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回はGビズID(GBIZ ID)について解説します!
GビズID(GBIZ ID)とは?
GビズID(GBIZ ID)とは、法人や個人事業主向けの共通認証システムです。GビズIDを取得すると一つのID・パスワードが付与され、インターネット上で補助金の申請や手続きの届出など様々な行政サービスを利用することができます。
アカウントを1つ取得すれば、有効期限、年度更新の必要はなく利用できます。(令和3年8月現在)
取得したアカウント情報は大切に保管しましょう。
また2020年11月よりe-Gov(電子政府の総合窓口)の電子申請サービスも、GビズIDで利用可能となりました。利用できる行政サービスは年々拡大しています。GビズIDで利用できるサービスの一例
ものづくり補助金、IT導入補助金などの申請
経営力向上計画や事業継続力強化計画などの認定申請
社会保険手続き
飲食店の営業許可申請
など
GビズIDによる電子申請のメリット
GビズIDは各種手続きの電子申請が可能です。電子申請には以下のようなメリットがあります。①いつでもどこでも手続き可能
インターネットを利用するため、24時間365日、自宅でも職場でも、申請や手続きができます。(サーバーのメンテナンス等により休止する場合あり)②時間・コストの削減
書類の提出に役所等に行く労力、移動時間、交通費が不要になります。また書類の郵送代も削減できます。③情報入力の手間削減
過去の申請などで入力した情報(企業概要や財務情報など)はその後も利用できるので(自動転記)、その都度入力の手間を省くことができます。④書類のハンコが不要
ログイン時の認証機能で申請者を確認するため、その都度書類に押印する必要がなくなります。まとめ
今までは法人・個人事業者の確認手段として電子証明書の取得(有料)が必要でしたが、GビズIDを取得すれば、電子証明書なしでも電子申請が可能となります。
GビズIDアカウントで利用できる行政サービスは今後も広がる見込みです。この機会にぜひGビズIDについての理解を深め、積極的にビジネスへ活用していきましょう。
助成金なうはこちら